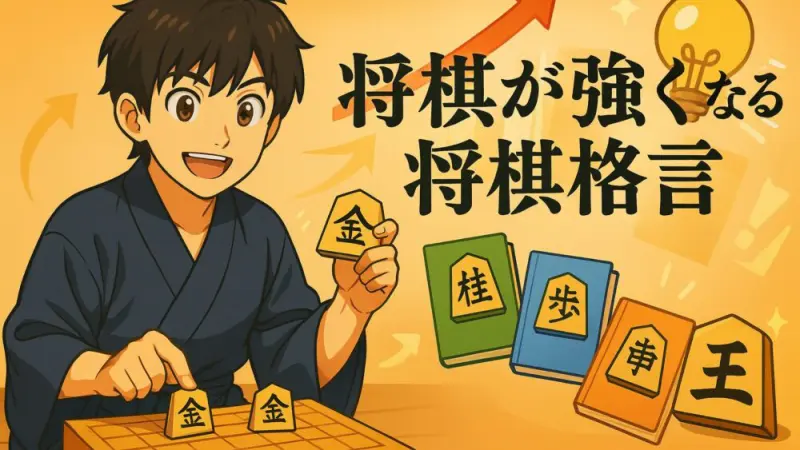- 将棋の格言を知りたい
- 序盤、中盤、終盤ごとの格言も知りたい
- 初心者にもわかりやすい動画で格言が理解できる
- おすすめの将棋格言本を教えてほしい
定跡通りに進まない将棋で、何を指せばいいか迷っていませんか?序盤の駒組みでほころび、時間に追われて逆転…そんな悩みは“格言”で解けます。
格言は膨大な実戦から抽出された再現性の高い判断ルール。本文では用途×意味の二軸で整理し、序盤の安全度向上チェック、中盤の働き化手筋、終盤の速度設計、誤用と例外条件まで具体化します。
読むほどに形勢判断が速くなり、候補手の検索コストが激減。勝ちやすい選択を積み重ねられます。結論、格言は丸暗記ではなく“使いどころ”を学ぶことで武器になります。
プロの知見や実戦データを踏まえたチェック表、フェーズ別テンプレ、誤用を防ぐクイック判定、学習を加速する合言葉まで網羅。
初心者から中級者まで、今日の一局で即使える“安全で速い思考”を手に入れましょう。動画と推薦書籍への導線も用意し、繰り返しの復習まで支援します。
将棋格言は実戦の知恵袋

将棋格言とは経験則の圧縮データ
将棋格言は、過去の膨大な対局経験から抽出された再現性の高い判断の指針です。完全なルールではなく、局面の大勢を早くつかむための「優先順位表」と理解すると役立ちます。
例えば「居玉は避けよ」は、例外がありつつも九割方で安全側に寄せる意思決定を助けます。格言を知ることは、形勢判断・候補手の抽出・リスク管理の三点で初心者の上達を加速させます。
さらに格言は、パターン認識を短時間で呼び起こす“トリガー”の役割も担います。
道路標識が「減速」「合流」を一瞬で伝えるのと同じように、「玉飛車接近すべからず」と目にした瞬間、横利きの衝突や両当たりの危険が脳内に展開されます。
定跡が“最善手の地図”だとすれば、格言は“危険領域を避けるための標識”です。地図がなくても、標識だけで迷わず進める場面が実戦には多く存在します。
また、格言は統計的に優位な選択を示す“勝ちやすい指針”でもあります。たとえば居玉のまま開戦すると、同等の実力同士では中終盤で逆転されやすい傾向が見られます。
これは一手一手の当たりに対する受けの自由度が下がるためです。格言はこの“自由度の確保”という抽象的価値を、短い日本語に圧縮して伝えています。
“羅列型”では覚えにくい【用途と意味で束ねる利点】
辞典型の用語集は便利ですが、単独のフレーズはどの場面で効くかが曖昧になりがちです。
本稿では「序盤の駒組/中盤の駒効率/終盤の速度」といった用途別、および「攻め・受け・玉形・駒の性質」といった意味別に整理し、使いどころ・例外・誤用まで一体で学べるように構成します。
用途別に束ねると、対局中に「今は玉形の安全を上げるフェーズか/働きの総量を増やすフェーズか/速度で押し切るフェーズか」を即断できます。
意味別に束ねると、同じ格言でも目的語が変われば解釈が変わる点に気づけます(例:「下段の香」は“受けの制空権”を拡張する文脈では強いが、攻めの最前線では過小)。
この二軸で整理しておくと、学習段階での暗記効率が上がるだけでなく、実戦での検索コストが下がり、思考に余白が生まれます。
さらに、用途×意味の二軸は例外条件の発見にも向きます。例えば「飛車先の歩交換」は“攻めの加速”という用途ですが、「角道が通ったまま」「2七地点が薄い」という意味要因が重なると危険度が跳ね上がります。
こうした相殺・増幅の関係をメモしておくと、格言の“効く範囲”が明確になり、誤用が減ります。
状況判断のスピードアップ
格言を学ぶことで、状況判断が非常に速くなるのは確かです。これは特に、相手が意外な手を指したときや、自分が予想外の状況に陥ったときに有用です。
そのような瞬間に迷ってしまうと、局面が不利になる可能性が高くなります。しかし格言があれば、すぐにでも何をすべきかのヒントを得ることができます。
加えて、状況判断の速度を上げることは、時間制限のある将棋においては特に重要です。制限時間内に最適な手を指すためには、速やかな判断が不可欠です。
格言はそのような制約下で、瞬時に「ベストな行動」を導き出すための貴重なツールとなっています。
このように、格言は複雑な局面やプレッシャーのかかる状況での判断を素早く、かつ正確に行えるようサポートしてくれます。
それはまるで、道を行く途中で突然迷ったときに、すぐに正しい方向を示してくれるような存在です。状況判断のスピードを高めるためにも、格言の学習とその活用は非常に有用なのです。
序盤に役立つ将棋格言とその使い方

五つの基本格言と要点
早石田・対振り・居飛車互角形など“駒組みの安全性”に直結する格言群です。序盤でのミスは取り返しが利きにくい構造的欠陥になりやすく、以後の中終盤の選択肢を狭めます。
ここで紹介する格言は、玉形の安全度・駒の連結・先後の主導権といった基礎評価を一気に底上げし、最初の10手〜30手を質高く進めるための土台になります。
| 格言 | 意味(平易訳) | 使いどころ | 典型的な誤用・例外 |
|---|
| 飛車先の歩交換三つの得あり | ①手持ち歩②相手陣形の乱れ③飛車の前進余地 | 相居飛車の相掛かり・角換わりなど | 角道が通ったままの反撃や、持ち歩を即打ちされる筋に注意 |
| 居玉は避けよ | 玉は早めに囲いへ | 開戦が早そうな将棋/角交換系 | 早仕掛けの受けに忙しい時は短手数で最小限の安全を優先 |
| 玉飛車接近すべからず | 王と飛車は離す | 開戦前の配置調整 | 横利き遮断で両狙いを受けづらくする意図。距離が近いと両当たりが生じやすい |
| 攻めは飛車角銀桂、守りは金銀三枚 | 攻めは射程+跳躍、守りは粘り | 攻め駒の編成/囲いの強化 | 金を攻めに出し過ぎると受け崩壊。終盤の寄せ用に金を温存する選択もあり |
- 「飛車先交換」は角の打ち込み筋(8八角成等)と2七地点の受けを事前に解決してから行うと安全です。
- 「居玉回避」は“囲い完成”が目的ではありません。まず横利きの直線上から外す一手でも十分に効果があります。
初心者向け“駒組みチェック表”
| 項目 | 基本方針 | チェックポイント | NGサイン |
|---|
| 玉 | 2〜4手で最低限の囲い(美濃/舟/矢倉入口)。開戦が見えたら「一歩外す」。 | 退路とコビン(斜め上)に利き/金1枚が玉側/囲いの入口が完成。 | 居玉のまま開戦/退路・コビンが空く。 |
| 飛車 | 横利きが自玉に重ならない位置。金銀と一直線にしない。 | 飛車筋と玉・金銀が重ならない/玉飛車接近を避ける配置。 | 玉飛車一直線/筋違い配置で利きが死ぬ。 |
| 角 | 利きを通すか止めるかを事前に決める。角交換に備え角頭(7七/3三付近)を補強。 | 角道の開閉理由を説明できる/角頭に守り駒がある。 | 角頭放置で焦点を突かれる/交換後に急所が露出。 |
| 歩 | 飛車先・端歩は攻防のスイッチ。突く理由を言語化し、突き捨て後の「取り返す駒」まで想定。 | 突き捨て→何で取り返すか決めている/端歩の位・突き合いの意図がある。 | 理由なき前進/取り返す駒不在で孤立。 |
| 金銀 | 金は玉の一枚傘、銀は前線の柔軟役。金は前に出し過ぎない。 | 金が玉側に残る/銀が攻防に働ける/金頭が薄くない。 | 金の前進で戻りに手数/金頭の空洞化。 |
| 端攻め | 9筋/1筋の位取りは「受けのスイッチ」。突き合わせ前に香の退路を確認。 | 香の退路(1二・9八など)を確保/端の受け駒と利きが通る。 | 香が詰む形/突き合いで自陣が窮屈。 |
| 先後のプラン | 先手は主導権、後手はカウンターの地合い。同じ格言でも先後で優先度は変わる。 | 先手:仕掛け筋と先手番活用/後手:受けの形と反撃の狙いを準備。 | 先後を無視した同一プランで無理攻め・受け一辺倒。 |
中盤の駒を働かせる将棋格言と応用例

五つの基本格言の“働き化”
形勢の差は「駒の働きの総量」で決まる——効いていない駒を動かすのが最善手になることが多いです。
ここからは、“働きの総量”を上げる具体的な動かし方を手筋+チェック項目で体系化します。
駒得や華やかな王手よりも、まず「眠っている駒をゼロにする」ことが結果的に最短の勝ち筋につながります。
| 格言 | コアアイデア | 代表的な手筋 | 例外・注意 |
|---|
| 遊び駒を活用せよ | 眠っている駒を前線へ | 歩の突き捨て→銀の繰り出し | 無理な進出は逆に“遊び駒の交換”に |
| 桂先の銀定跡なり | 桂頭(桂の前)に利きを足す | ▲…銀打/進で桂の着地点を封鎖 | 自分の玉頭が薄いと逆用される |
| 焦点の歩に好手あり | 利きの交差点に歩を打つ | “同×なら別の利き”の分岐を作る | 打ち歩詰め・二歩等禁じ手に注意 |
| 竜は敵陣に、馬は自陣に | 竜=制圧、馬=要塞化 | 竜で横利き制圧/馬で玉頭補強 | 竜を下段で守備に回すと過小評価に |
| 角の頭は丸い | 角の正面は盲点 | 角頭に歩打→突破 | 角の退路(斜め)を塞がれると逆転筋 |
- 遊び駒:まず“盤端の重い駒(香・桂)”を棚卸しします。位取り→前進の通路作り→合流の三段で働かせます。無根拠の前進は、相手の軽い一手で交換されるのがNG。
- 桂先の銀:桂の着地(跳ね先)と頭(その前マス)のどちらが弱いかを先に判定。銀で利きを足す/押さえるの区別をつけ、玉頭が薄い側での適用は回避します。
- 焦点の歩:取らせる→別筋で回収、もしくは拠点化の二択を事前に用意。**禁じ手(打ち歩詰め・二歩)**の確認を声に出してから指します。
- 竜・馬の役割:竜は“横利きの制圧線”を一本通せる地点(5段目〜敵陣)に置くのが基本。馬は自陣の**要所(玉頭/金頭)**に利きを合わせて受けの網を強化します。
- 角頭攻略:角の退路(斜め線)を先に塞ぐ→角頭を叩く、の順番がセオリー。退路確保済みの角頭叩きは空振りになりがちです。
終盤を制する格言と勝ち切るコツ

五つの基本格言の役割分担
終盤は速度と寄せ筋の簡素化。駒得より“詰み・必死の速さ”を優先します。
ここでは「速さ」を設計する具体手順と、囲い別・構図別のテンプレートまで踏み込み、勝ち切るための再現性を高めます。
| 格言 | ねらい | 典型図のイメージ | よくある内容 |
|---|
| かなめの金を狙え/金なし将棋に受け手なし | 囲いの要を外す | 美濃の頭(金)を剥がす | 金を追い回すだけで寄せが遅い |
| 玉は下段に落とせ | 逃走路の縮小 | 上部脱出を封じて“詰みの網” | 自分の下段が利き不足だと逆効果 |
| 金はとどめに残せ | 決め手の質を確保 | 最後の一押しは金打ち | 途中で金を切って速度低下 |
| 長い詰みより短い必死 | 実戦的な勝ちに短手数 | “受けなし”を先に作る | 無理筋で自玉が先に詰む |
| 終盤は駒の損得より速度 | 一手の価値が最大化 | 王手—合駒—取りのテンポ勝ち | 駒損が受けきかれると逆転 |
| 王手は追う手 | 詰めろ・必至を優先 | 王手より“要の地点”に利かし(金打・叩き) | 連続王手で持ち駒切れや上部脱出を許す |
| 玉は包むように寄せよ | 退路を段階的に封鎖 | 上から金・横から銀・下から歩で“包囲網” | 一直線の追撃で上部脱出を許す |
補足:これらは相互に作用します。例えば「金はとどめ」と「終盤は速度」は矛盾しません。最後の寄せ速度を最大化するために金を温存する、という関係です。
誤解されやすい格言とその補足

誤用しがちな格言リスト(要点整理)
| 格言 | よくある誤解 | 正しい理解 | 例局面のヒント |
|---|
| 玉は下段に落とせ | いつでも下段へ誘導すれば良い | 上部の利きが勝っているときは上へ追う方が早い | 相手の金銀の利き方向を見て“逆方向”に追う |
| 飛車先の歩交換三つの得あり | どんな形でも先行して得 | 角道・2七の受けなど前提条件が必要 | 角の打ち込み(8八角成等)の反撃を先に消す |
| 竜は敵陣に、馬は自陣に | 竜は守りに使ってはダメ | 局面の最重要マスを制圧できるなら守備竜も有効 | 自玉の詰めろ受けで竜の横利き活用 |
| 居玉は避けよ | 囲い完成まで戦ってはならない | 短手数の安全化(1〜2手の小ビショップ)で十分な局面が多い | 角交換早仕掛けでは金一枚の移動で十分 |
| 下段の香に力あり | いつでも下段に打てば強い | 自陣の厚みを縦に伸ばす受けの用途で真価。攻めの前線では過小 | 自玉側1一/9九に打ち退路を確保してから使う |
| 金はとどめに残せ | 金を使わないのが正解 | 中盤までは普通に活用する。終盤の決め手として1枚温存できると理想 | 寄せの最終形を想定し、金打ちの“着地点”を先に決める |
| 長い詰みより短い必死 | いつでも必死優先 | 詰みが見えるなら最短の詰みが最善。見えない時に必死で実戦優位 | 自玉の詰めろの有無→相手の受け札の在庫を先に点検 |
| 玉飛車接近すべからず | 近づけてはならない絶対規則 | “近接の副作用”(両当たり・利き遮断)を避けるのが目的。例外:受けに竜の横利きを通す | 斜め・横の利きが重なる筋を一本ずらすだけで改善 |
- いま適用しようとしている格言の“副作用”は何か?
- その副作用は一手以内に相殺できるか?
- 相手により大きい副作用(利きの分断・玉形の緩み)を強いる見込みはあるか?
※ 3つのうち2つ以上がYESなら、適用の価値が高いと判断できます。
例外が起きる“条件”を言語化する
- 玉形の相対差:相手の囲いが薄ければ、こちらが薄くても速度勝ちを狙える。
- 利きの交差点:焦点の歩は利きの総和で判断(自分>相手なら成立)。
- 持ち駒の質:歩・金・角の使い所で格言の優先度が入れ替わる。
- 手番と流速:相手の反撃が“王手—取り—王手”で連続するなら、受け→簡素な反撃を優先。
- 駒の偏在:片翼に駒が寄っている場合、逆サイドの端攻め・継ぎ歩が過大評価になりやすい。
- 盤面の温度:持ち時間・駒得/損・詰めろの有無で“速度価値”が変動。終盤寄りほど速度の重みが増す。
| 例外が発生しやすい信号 | 具体例 | 対応フレーズ |
|---|
| 手番を失うと一気に受けが利かなくなる | 相手の竜が横利きを通し、王手—取りが見える | 「詰めろ逃れに王手なし」→まず受けてから反撃 |
| 自陣の要所に“利きの穴”がある | 金頭・玉頭の空洞化 | 「かなめの金を狙え」の逆:かなめを補強してから攻める |
| 焦点に打つと禁じ手の恐れ | 打ち歩詰め・二歩の懸念 | 先に退路確保/利きの上書きで合法化してから実行 |
ひと言で言語化すると、**「例外は“速度・利き・合法性”のいずれかが満たせない時に起こる」**です。局面の温度を測り、どれを満たせていないのかを特定しましょう。
初心者が陥る“パターン病”の回避
格言を丸暗記→機械的適用すると、相手の狙いにハマります。常に「この一手の副作用は何か?」を口に出して確認しましょう。
副作用(利きを外す・玉形が緩む・遊び駒が増える)を一つでも相殺できるなら、その格言はその局面で“生きている”と判断できます。
- 副作用ジャーナル(対局後3分メモ)
- 今日使った格言/効いた局面/効かなかった理由/次回の修正案を一行ずつ記録。
効かなかった理由を「速度」「利き」「合法性」のどれに分類できるかをチェック。
次回の練習局面は“分類の逆”を作る(例:速度が足りなかった→詰めろ連続を作る課題局面)。
- 即修正のルール(その場でやり直す)
- 格言通りの第一感を紙上で一手だけ指してみる。
相手の最善応手を置く。
「副作用」が改善しない場合は、格言の“目的”だけ残して手段を差し替える
- ミニ格言 vs. 大格言の整合
- 「小さなセオリー(継ぎ歩・叩き)」が「大きな原則(速度・堅さ)」に反する場合、大原則を優先。
迷ったら「自玉の安全度→相手玉への到達速度→駒の働き」の順に並べ替えると判断が安定します。
格言の覚え方・実戦での活かし方

カテゴリ別に束ねて記憶する
- 玉形(居玉・玉飛車距離・玉は下段)
- 攻め(焦点の歩・飛角銀桂・金はとどめ)
- 守り(金銀三枚・下段の香)
- 駒の性質(角の頭・竜馬の役割)
カテゴリで束ねると、対局中に検索時間が短縮されます。さらに、各カテゴリに**合言葉(トリガー)**を付与すると、瞬時に想起しやすくなります(例:玉形=「自由度」、攻め=「速度」、守り=「厚み」、性質=「盲点」)。
| カテゴリ | 合言葉(判断軸) | 代表格言 | その場のセルフチェック |
|---|
| 玉形 | 自由度 | 居玉は避けよ/玉飛車接近すべからず | 王手に対する受けの選択肢は3通り以上あるか |
| 攻め | 速度 | 焦点の歩/攻めは飛車角銀桂 | 詰めろ or 受けなしが次の一手で作れるか |
| 守り | 厚み | 金銀三枚/下段の香 | 金の連結と横利き遮断は両立しているか |
| 性質 | 盲点 | 角の頭は丸い/竜は敵陣・馬は自陣 | 相手駒の弱点のマスを一つ言語化できるか |
コツ:合言葉は声に出すと効果が上がります。着手前に「速度」「厚み」と一言添えるだけで、候補手の粗さが減ります。
由来や背景で“意味付け”する
格言は実在の対局や定跡から生まれ、歴史的背景を知ると記憶に定着します。例えば「桂先の銀」は古典相居飛車の攻防から抽出されたもので、桂の弱点(着地と頭)を埋める合理性が由来です。
さらに、背景理解には次の三手順が有効です。
- 局面写真を作る:該当格言が“効く形”と“効かない形”を並べてスクショ(または盤面メモ)化します。差分を見ると適用条件が浮かび上がります。
- 物理直感に落とす:たとえば「玉飛車接近」は“重心が近いと一撃で崩れる”という直感に置き換えられます。抽象語を日常の比喩に変換すると忘れにくくなります。
- 逸話化する:自分の対局や観戦で見た印象的な一手を「格言タグ」付きで一言日記に。誰が・どの形で・どう効いたかの三点を残すと、次回の想起率が高まります。
初心者におすすめの将棋格言動画まとめ

女流棋士による将棋格言講座【玉を詰ます時編】
この動画では、将棋女流棋士の山口恵梨子さんが、終盤で相手の玉を詰ます際に役立つ3つの将棋の格言を紹介しています。
これにより、オンライン対局など持ち時間の短い対局でも、直感的に最善手を見つけやすくなると解説しています。
紹介された3つの格言は以下の通りです。
- 玉は包むように寄せよ: 相手玉の逃げ道をあらかじめ塞ぎながら攻めるという考え方です。
- 玉は下段に落とせ: 相手玉を下段に追い詰めて、詰ませやすくする考え方です。
- 玉の腹から駒を打て: 相手玉の横に駒を打つことで、相手玉を詰みに追い込む方法です。
動画ではこれらの格言が実際の盤面でどのように活かされるのか、具体的な手を示しながら分かりやすく解説しています。
これらの格言を学ぶことで、将棋の終盤力が向上し、勝率アップに繋がると締めくくられています。
女流棋士による将棋格言講座【玉を守る時編】
この動画では、将棋女流棋士の山口恵梨子さんが、自分の王を守る際に役立つ3つの将棋の格言を紹介しています。
この格言を知ることで、劣勢な状況でも粘り強く戦い、逆転の可能性を高めることができると解説しています。
紹介された3つの格言は以下の通りです。
- 玉の早逃げ 八手の得: 相手の攻撃を予測し、早めに王を安全な場所に逃がすことで、結果的に攻めに転じる手数を稼ぐという考え方です。
- 桂頭の玉 寄せにくし: 王を桂馬の頭の上に配置することで、相手が王を攻めにくくする考え方です。
- 中段玉は寄せにくし: 王を盤面の中央に逃がすことで、相手の駒の利きが届きにくくなり、攻めをかわしやすくなるという考え方です。
これらの格言は、窮地に陥った際にも冷静に最善手を判断する助けとなり、実践で非常に役立つと締めくくられています。
格言講座を覚えよう
この動画では、終盤の寄せを学ぶために役立つ4つの将棋の格言を紹介しています。
紹介された4つの格言は以下の通りです。
- 玉を包むように寄せよう: 相手の玉を逃がさず、包囲するように攻めるのが効果的です。単純に馬を切って金で挟み撃ちにする手や、歩を活用する手など、状況に応じた寄せが解説されています。
- 玉は下段へ落とせ: 相手の玉を上に逃がさず、下段に追い詰めていくのが重要です。
- 端玉には端歩: 盤面の端にいる相手の玉を詰めるには、端の歩を活用する格言です。プロ棋士も有効と認める手筋であり、他の手では詰みにならない場合でも、この格言を応用することで詰みに持っていくことができると紹介されています。
- 玉の腹から銀を打て: 相手の玉の横(腹)に銀を打つことで、相手の受けを困難にし、詰みに追い込む非常に有効な攻め方です。
これらの格言を覚えることで、終盤の寄せの形をイメージできるようになり、勝率を上げることにつながると解説しています。
【藤倉勇樹チャンネル】第二弾!格言を覚えよう!前編
この動画では、実戦で役立つ将棋の格言「両取り逃げるべからず」について解説しています。
これは、2つの駒を同時に狙う「両取り」をかけられた際に、守るのではなく、あえて攻めに転じることで優位を築くという考え方です。
動画では、飛車と金が両取りにかけられた局面を例に挙げています。初心者は飛車を逃がしがちですが、この格言に従えば、飛車を犠牲にしてでも攻めを継続する方が、結果的に勝率が高くなると解説しています。
相手に飛車を取らせる間に、自分の攻め駒を最大限に活用して、一気に寄せ切るのが正しい対応です。
終盤戦では、相手の玉が「絶対に詰まない形」であることを確認した上で、自分の駒の価値を最大限に活かすことが勝利につながると強調しています。
この格言を学ぶことで、両取りに動揺することなく、冷静に最善手を見つけられるようになるでしょう。
【藤倉勇樹チャンネル】第二弾!格言を覚えよう!後編
この動画では、実戦の終盤で非常に役立つ格言「桂頭の玉寄せにくし」について、具体的な局面を例に挙げて解説しています。
この格言は、自分の玉を相手の桂馬の頭の上に配置することで、相手から王手をかけられにくくし、玉の安全を確保するという考え方です。特に相手の攻め駒に角の利きがない場合などに有効です。
動画内では、以下2つの局面を解説しています。
- 1つ目の局面: 相手の「9五桂」に対して、安易に玉を引いてしまうと、挟み撃ちにされて厳しくなる可能性があるが、格言通り「9六玉」とすることで、玉の安全を確保できる。
- 2つ目の局面: 相手の「3六同桂」に対して、「1七玉」と端に逃げたくなるが、それでは「端玉には端歩」の格言通りに攻められ、不利になる可能性がある。正解は「3七玉」とすることで、この「桂頭の玉寄せにくし」の形を作り、相手の攻めをかわすことができる。
このように、状況に応じて最適な格言を選ぶことで、終盤で迷うことなく正しい手を指し、勝率を上げることにつながると解説しています。
おすすめの将棋格言本3選

目からウロコ!今どき将棋格言
書籍「目からウロコ!今どき将棋格言」は、将棋の古今の格言を通じて正しい指し方を明快に示す内容で構成されています。
青野照市著者によるこの書籍は、将棋格言を3つのカテゴリに分けて取り上げています。
それは、著者オリジナルの新格言、既存の格言を現代の将棋に合わせて表現を変えバージョンアップした格言、そして古今不変の格言です。
いくつかの新しい格言は著者自身が作成し、その知恵は著者の体験から生まれたものになります。
青野照市著者が提供する新格言の例としては、「おいしい駒とまずい駒」「王手の八割は悪手」「敵の逃げたい場所に打て」といったものがあります。
これらの格言は、古くから伝わる将棋の知恵を現代のプレイヤーに伝えるだけでなく、新しい視点を提供し、現代の将棋の環境に合わせてアップデートされたものとなっています。
また、格言を通じて将棋の基本的な原則や戦術を理解することで、プレイヤーはより効果的な対局を展開できるようになるでしょう。
 ポチップ
ポチップ
渡辺明の 勝利の格言ジャッジメント 飛 角 桂 香 歩の巻
渡辺明による「勝利の格言ジャッジメント 飛 角 桂 香 歩の巻」は、将棋ファンに向けた、飛車、角行、桂馬、香車、歩兵の各駒に関連する格言を探求した書籍です。
この書籍は、各駒の特性や戦術に焦点を当て、これらの格言がどのようにプレイヤーの戦術や戦略に影響を与えるかを考察しています。
この書籍の中で渡辺明棋士は、多くの将棋の格言について現代的な視点から分析し、それらの格言がどのようにトッププロの将棋プレイヤーによって評価されているかを明らかにしています。
特に、振り飛車に関連する格言や実戦での格言の適用について深く探求しており、読者に対して振り飛車や居飛車の戦術を理解する手助けをしています。
また、この書籍は、Eテレの「将棋フォーカス」で2015年10月から2016年3月まで放送された講座「渡辺流 勝利の格言ジャッジメント」の放送テキストを基に、加筆・再構成されて単行本化されたものであり、将棋の理解をさらに深める内容になっています。
 ポチップ
ポチップ
渡辺明の 勝利の格言ジャッジメント 玉 金 銀 歩の巻
渡辺明の著書「勝利の格言ジャッジメント 玉 金 銀 歩の巻」は、将棋の格言について現代的な視点から分析し、評価する内容となっています。
この書籍は、渡辺明の 勝利の格言ジャッジメント 飛 角 桂 香 歩の巻の姉妹本です。2冊揃えることで各駒についての格言を網羅できます。
将棋の格言は数多く存在するものの、時代と共に感覚や考え方が変化するため、格言の真実性を渡辺明氏が現代的な視点から判断し、紹介しています。
各巻には50余りの格言が収載されており、将棋ファンにとっては必読の一冊とされています
書籍の内容に関しては、将棋の格言が多数存在する中で、その格言が実際にはどれだけ真実であるのか、そして昔と今とで感覚や考え方がどれだけ違うのかを渡辺明氏が現代的な視点から分析し、評価を行っています。
また、書籍は将棋界の第一人者による判断を含んでおり、将棋ファンにとっては非常に価値のある内容となっています。
 ポチップ
ポチップ
まとめ
この記事では、将棋格言の実戦活用について解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 格言=経験則の圧縮データ。「用途×意味」の二軸で束ねると、局面での想起が速くなり、形勢判断・候補手抽出・リスク管理が同時に整う。
- **序盤・中盤・終盤で役割が違う。**序盤は安全と連結(居玉回避/玉飛車距離/+駒組みチェック表)。中盤は“遊び駒ゼロ化”と焦点の歩・竜馬の使い分け。終盤は“速度と寄せの簡素化”(かなめの金/下段に落とす/必至づくり)。
- **誤用は条件不足が原因。**例外は「速度・利き・合法性」のいずれかが欠ける時に起こる。着手の“副作用”を言語化し、「副作用ジャーナル」で学習を回すと再現性が上がる。
将棋格言の実戦活用では、**「用途×意味の二軸整理」と「速度・利き・合法性チェック」**が重要なポイントとなります。
将棋格言の実戦活用では、ぜひこのポイントを押さえて、次の対局で**「駒組みチェック表」と「副作用ジャーナル」**を試してみてください。他の入門記事は、はじめて将棋を指す!最初の一歩としての入門必読記事まとめもどうぞ。
この記事を書いた人

ゆる
将棋ブロガー/アマチュア初段
10代で将棋を覚えましたが、当時は定跡を知らず挫折しました。大人になって将棋熱が再燃し、詰将棋と定跡を集中的に学習。将棋ウォーズで5級→2級→1級と昇級後、停滞期を経て、PDCAの徹底と師匠の指導により初段に昇段しました。現在は指し将棋を休止し、将棋ブログの執筆に注力しています。
将棋歴:12年/段位:アマチュア初段
資格・実績:将棋ウォーズ初段 達成率最高86%/将棋倶楽部24 最高R716
- 将棋ルール解説
- 将棋の上達法
- 初段になる方法
- 用具の選び方