PR
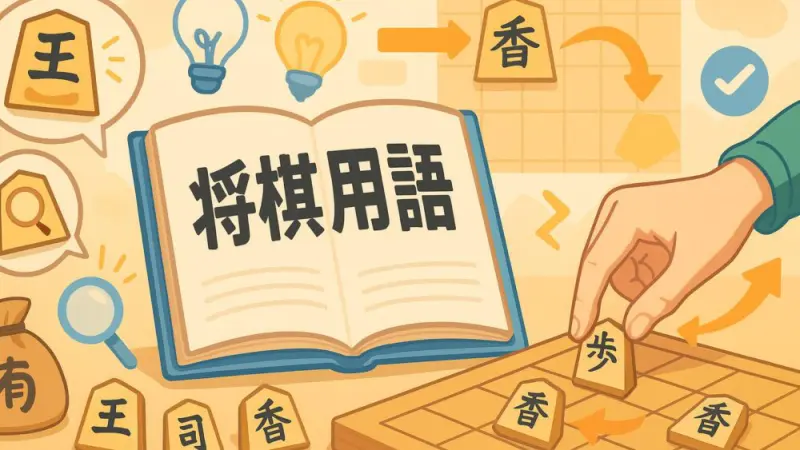
- 将棋観戦や定跡学習などでわからない単語が出てきた
- 今日から使える将棋用語が知りたい。
- おすすめの将棋用語本があれば知りたい
「王手」と「詰み」の違い、説明できますか?実況やSNSで飛ぶ将棋用語が曖昧で、対局中に手が止まっていませんか?
用語は“盤上の視点”そのもの。本記事は、観戦・感想戦・AI解析で頻出の語を、初心者でも今日から使える順にやさしく整理します。
基本の「打つ・成る・王手」、禁じ手、戦法の入口、評価語の見分け方、学習の4週間ロードマップまで一気に解説。
用語がわかれば、読みの速度と精度が上がり、勝ち筋の発見も早くなります。言葉から強くなる近道を、今すぐ始めましょう。
さらに、ミニ実戦譜で“利き・狙い”を体感し、似た用語は表で一発整理。迷いがちな「詰めろ判定」「受けの一手」もチェックリストで即判断出来ます。
もちろん初心者がつまずく二歩や打ち歩詰めなどの反則も、理由つきでスッと理解できます。観戦の満足度、感想戦の伝わり方、オンライン対局の勝率まで、あなたの将棋体験がまるごと変わります。
将棋用語を知れば将棋がもっと楽しくなる

なぜ「用語」が強くなる近道なのか
将棋は「盤上の会話」ともいわれます。解説や観戦記では短い言葉で多くの情報を圧縮して伝えます。
例えば「▲先手が玉の早逃げ」「△角の利きを通した」など、一語で“形勢判断・狙い・リスク”まで含みます。用語を理解すると、対局の意図が素早く読めるようになり、実戦での選択も速くて正確になります。
さらに、言葉は“視点”を与えます。「受けの一手」「利きを通す」「厚みを築く」といった表現は、どこを見れば良いかを示す道標です。
言葉を知る→盤面で探す→実戦で試す、という循環が回り始めると、同じ局面でも見える情報量が増え、終盤の読みの精度も上がります。
たとえば「捨て駒で玉形を乱す」という言い回しを知っているだけで、寄せの局面で“取らせて得する手”を候補に挙げられるようになります。
観戦の満足度、感想戦での会話の深さ、AI解析の理解度まで、すべてが一段引き上がります。
本記事の目的と範囲
本記事は、初学者が今日から使える基本用語を中心に、由来や覚え方のコツまで段階的に解説します。対象は「駒の名前・基本動作・局面や評価・解説で飛び交う語」。
定跡(オープニングの定跡集)や細かな戦型名は入口だけ触れ、学習ステップの中で自然に広げます。
あくまで“実戦・観戦に直結する語”を優先し、専門性の高い派生用語(細部の囲い名称のバリエーション、型番のような戦型記号など)は後半の学習ステップに回します。
初めての方でも挫折しないよう、各用語には短い用例とミニTipsを添え、混同しやすい近縁語は表で整理します。これにより、学習の全体像(何を先に覚え、何を後回しにするか)が明確になります。
本記事の読み方
専門語はやさしい日本語で補い、必要に応じて例文を添えます。棋譜の符号(例:▲7六歩)は“黒三角=先手、白三角=後手”の意味で、数字はマス目の座標です。
先に書かれる数字が筋(縦の列)、後の数字が**段(横の段)**を示し、「7六歩」は“7筋6段の地点へ歩を進める”の意味です。
(読みは「ななろくふ」)同一地点での取り合いは「同歩」「同金」のように“同”で表します。また、▲は先手、△は後手を示し、環境によっては☗(先手)・☖(後手)と表記されることもあります。
成りは「成」、打つは「打」で表記され、「金打」「成銀」のように末尾に付くのが慣例です。
符号が苦手でも、本文の例文だけで理解できる構成にしており、スマートフォンで読む方のために一文を短く区切り、重要語は太字で強調しています。
必要に応じて盤面イメージを思い浮かべながら、声に出して用語を確認すると定着が速まります。
初心者がまず覚えたい基本用語10選

はじめに“頻出かつ効果が高い”10語をまとめます。
用語は意味といつ使うか(場面)で覚えると定着します。さらに、似た語との境界と反則(禁じ手)との関係まで押さえると、実戦で迷いにくくなります。
ここではそれぞれの用語に“初心者メモ”を添え、短時間で要点を思い出せるようにしました。
| 用語 | 読み | 簡潔な意味 | 使う場面の例 | 初心者メモ(覚え方) |
|---|---|---|---|---|
| 王(玉)将 | おう(ぎょく)しょう | 自分(相手)の大切な駒。取られたら負け | 玉の安全を優先する判断で「玉の早逃げ」 | 最後まで守る“王様”。囲い=王の家作り |
| 飛車 | ひしゃ | 直線に何マスでも動ける大駒 | 横・縦の制圧、攻めの主力 | 「車線」を走るイメージで一直線に強い |
| 角行 | かくぎょう | 斜めに何マスでも動ける大駒 | 斜めの利きを通す、両取りの狙い | 斜めの“角度”で走るから角行と覚える |
| 金将 | きんしょう | 守備と寄せの要。斜め後ろ以外に一歩動く | 玉周りを固める「囲い」で活躍 | “金庫番”=守りの要。寄せでも強い |
| 銀将 | ぎんしょう | 斜めの動きに強い。攻めの連結役 | “銀が泣く”=戻りにくい形を戒める言い回し | 攻めの“斜め役”。前へ出す時は戻り道意識 |
| 歩兵 | ふひょう | 一歩ずつ前進。敵陣で成ると「と金」 | タテの圧力、受けの一手「突き捨て」など | 兵隊は一歩ずつ。成ると金並みに強化 |
| 王手 | おうて | 相手玉に次で取るぞと迫る手 | 詰み筋の起点。うっかり王手は禁物(手番を渡す) | 王手=相手の“強制手”。意味なく連発しない |
| 詰み | つみ | 玉がどこにも逃げられない終局 | “詰め上がり”を読む練習が上達の近道 | 終局ワード。受けゼロ=ゲームセット |
| 打つ | うつ | 手持ちの駒を盤上に置く | 「歩を打つ」「金打ち」など持ち駒を使う動作 | 手札を盤に置く。打ち歩詰めは反則に注意 |
| 成る | なる | 敵陣で駒を裏返し強化する | 「成銀」「龍(りゅう=成った飛)」など | 敵陣で“昇格”。成るか否かは選べる場合あり |
「王手」と「詰み」は別もの
王手は“チェック”で、相手は必ず受けなければいけません。詰みはその受けが一手もない状態で、対局は即終了です。
両者を混同すると終盤でミスが増えます。実戦では「王手病(何でも王手)」に注意し、詰むか詰まないかの判定を優先します。
例えば、終盤に相手玉へ王手をかけるより、自玉が詰む順を消す「受けの一手」を指す方が勝率は上がることが多いです。
王手は“強制力が高い”反面、相手に良い受けを与えると手番を失い逆効果になることもあります。まずは「王手→詰み筋に直結するか」「詰めろ(次に詰む脅し)になっているか」を落ち着いて確認しましょう。
「打つ」と「成る」の最小ルール+禁じ手の基本
持ち駒は自陣・敵陣どこへも打てますが、歩の二歩(同じ筋に歩を二枚)は反則です。
「成るのは敵陣(三段目)に入ったときで、成る・成らないの選択が可能な駒と、成りが必須の駒(行き所のない駒を避けるための成りなど)があります。」
成った後の名称(例:と金、成銀、龍・馬)もセットで覚えると、解説がスムーズに理解できます。
併せて、初学者がつまずきやすい**禁じ手(反則)**を要点だけ押さえておくと安心です。
| 反則名 | 内容の要約 | なぜ反則か(理由) |
|---|---|---|
| 二歩 | 同じ筋に自分の歩を二枚並べて打つ・動かす | 無限に受けに使える不公平が生じるため |
| 打ち歩詰め | “歩を打つ”一手で相手玉を詰ませる(他の受けがない) | 単純な打ち歩での詰みを禁じ、手筋の多様性を保つため |
| 行き所のない駒 | 打った駒や進んだ駒が進退不能になるマスへの着手(例:成れない地点に桂を打つ) | ルール上その駒が合法的に次手以降動けない状態を作るため禁止 |
打ち歩詰めは、歩以外の駒が関わる合い駒や逃げ道を一手前に作ることで合法ルートに変わることが多く、寄せの手順構成を学ぶ良い題材になります。
例で実感する基本動作(ミニ実戦譜)
例1:「▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩」――先手は右辺から飛車先を伸ばし、後手は左辺から角の利きを通す準備です。数手のやり取りにも“利き・狙い”が隠れています。
例2:「▲2五歩 △同 歩 ▲同 飛」――先手は飛車先の歩を交換して横の制圧力を得ます。ここで「△3三角」と受けられると飛車の横利きが止まり、角交換の含みも生じます。基本用語の組み合わせ(交換・利きを通す・受けの一手)を意識しましょう。
例3:「▲8八銀 △3四歩 ▲7七銀」――角道を閉じつつ、銀を使って堅さと手厚さを作る進行です。金銀の役割を理解すると、囲いの言葉(美濃・矢倉など)にも自然に橋がかかります。
盤面を見ながら声に出して読むと、用語と動作がリンクして記憶に残ります。最初は短い定跡並びや詰め上がり図で“王手→受け→詰み(または不詰)”の流れを追うだけでも効果的です。
対局で頻出する状況別用語

| 区分 | 代表語 | 要点 | 初心者向けの覚えどころ |
|---|---|---|---|
| 戦法・対局条件 | 居飛車・振り飛車/平手・駒落ち | 飛車を右(居)に置くか左(振)に回すか/駒を等しく並べるか手合いを変えるか | まずは居飛車から。相手の振り飛車には“角の利き”と玉の堅さで対処 |
| 評価・形勢 | 好手・妙手/悪手・疑問手/詰めろ | 手の良し悪しと相手への具体的な脅威を端的に表す | “詰めろ”は次に詰む脅し。受けを強要できる |
| マナー | 「お願いします」「ありがとうございました」「投了」「感想戦」 | 始まりと終わりの挨拶・投了の作法・対局後の検討 | 感想戦は上達の宝庫。負けても礼を尽くす |
| フェーズ区分 | 序盤・中盤・終盤 | 目的が異なる三段階。序盤=駒組み、中盤=攻防の主導権争い、終盤=寄せ合い | いまはどのフェーズかを口に出して確認すると方針がぶれない |
| 囲い・玉形 | 矢倉・美濃・穴熊・舟囲い | 玉の家の形。堅さと手数のバランスで選ぶ | “堅さ”と“速さ”のトレードオフを意識 |
| 時間・手番管理 | 先手番・後手番/持ち時間・秒読み・フィッシャー | 先後と時間配分は勝敗を左右。秒読みでは“ワンポイント読み”に切り替える | 残り時間を毎手確認。荒い手順は時間不足のサイン |
| 形の評価語 | 厚い・薄い・重い | 駒の連結と働きの良し悪しを指す | 厚い=守攻両用で崩れにくい/薄い=切れやすい/重い=駒が前に出すぎて後が弱い |
| 終盤警報 | 必至・寄せ・両取り | 勝敗直結のキーワード。必至=“受けても詰む”、寄せ=“詰みを目指す連続攻め” | 必至は詰めろの最終形。受け方がなければ投了が礼儀 |
| 受けと攻めの転換 | 受けの一手・受けなし・受けに利かす | 受ける/受けないの判断軸と、受けながら次の攻めの芽を作る思考 | 受けは“時間を買う”行為。次の反撃(利かし)とセットで考える |
【戦法の入り口】居飛車と振り飛車
居飛車は直線制圧で主導権を取りやすく、振り飛車は飛車の位置を変えてカウンターを狙います。どちらも正解です。まずは得意を一つ決め、相手が逆の戦法でも“角の利き”と“玉の堅さ”で対抗します。
もう一歩踏み込みます。居飛車は序盤に飛車先の歩交換で横の制圧力を確保しやすく、角筋を活かした両取りの狙いが作りやすい反面、玉が戦場に近づきやすい点に注意します。
振り飛車は玉を美濃囲いに囲い、飛車を反対翼に回すことで、相手の攻めを受け止めつつ反撃する設計です。どちらを選ぶかは、
- 早い攻めで主導権を握りたい→居飛車寄り
- 受けて反撃、バランス型で戦いたい→振り飛車寄り
という性格面も参考になります。練習の際は、同じ定跡並びを左右反転させて眺めると、戦法間の共通項(角の利き・玉の堅さ・主戦場)が見えてきます。
【評価語の使い分け】好手/妙手/疑問手
好手は素直に価値が高い一手、妙手は一見損でも全体最適を生む一手です。例えば、終盤で“捨て駒”により玉形を乱し、次の寄せが一気に通るならそれは妙手の典型です。
疑問手は致命傷ではないが最善を逃した手で、悪手は明確に損。実況や解説のニュアンスが分かると、棋譜並べの焦点が絞れます。
判定のコツは三軸です。①駒得・駒損はないか、②手番の維持に資するか、③玉の安全を損なっていないか。三つのうち二つを満たす手は概して好手寄りです。
もう一つ、初学者が伸びる近道は**“詰めろ判定”の口癖化です。「この手は詰めろか?」「相手の狙いは詰めろか?」と自問するだけで、次の一手の優先度が整理されます。
妙手に飛びつく前に、まず悪手を避ける**ことが上達の近道である点も忘れないでください。
【マナーと言葉】投了と感想戦
勝敗がはっきりしたら潔く投了。形勢が大差で“受けなし(受けても意味がない)”と判断したときは、無理な粘りより礼を優先します。
言い方は簡潔に「投了します。ありがとうございました。」が基本です。オンライン対局でも同様で、切断や放置はマナー違反とされます。
感想戦では、事実確認→仮説→代案の順で話すと生産的です。例えば「この局面で△4四歩を考えました。以下、▲同歩ならどうでしたか」のように、用語を交えて意図を述べると相手にも伝わりやすくなります。
強い相手ほど、敗因の特定よりも再現可能な学び(“この筋は危ない”“玉の早逃げの好機”など)を重視します。最後に、自分の課題を一言でまとめておくと、次局の観戦・練習の焦点が定まり、上達が加速します。
上級者の解説で使われる将棋専門用語
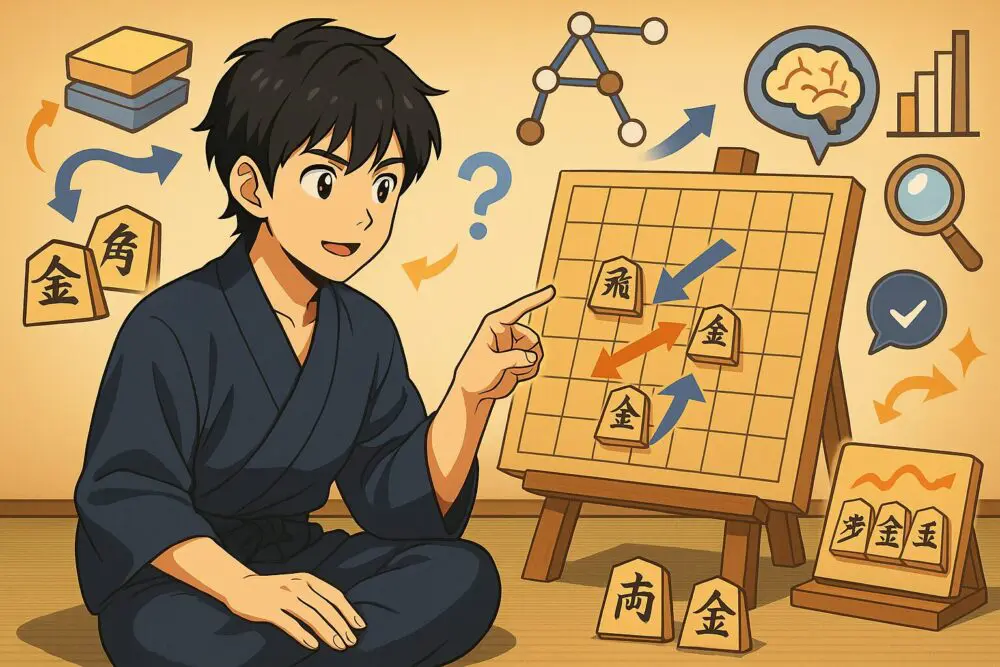
| 用語 | 意味 | 一言ヒント |
|---|---|---|
| 捨て駒 | あえて取らせて利きを通す犠牲の一手 | 終盤の寄せで発動する“時間の買い物” |
| 駒得/駒損 | 交換で得た(失った)駒の価値差 | 点数感覚=終盤の勝ちやすさ |
| 手順 | 一連の狙いを実現するための手の並び | 「手順前後」は順番ミス |
| 手筋 | 形に現れる“筋の良い”着手パターン | 反復で“見える化”する |
| 切れ筋 | その先が途切れて失敗する読み筋 | 途中で詰まる道は捨てる |
| 合駒 | 王手のラインに駒を“合”わせて受ける | どの駒で合うかで差が出る |
| 玉の早逃げ | 早めに安全地帯へ逃がす受けの手 | 「受けの一手」は守りの要所 |
| 遊び駒 | 役目を果たさず遊んでいる駒 | 仕事を与える配置転換で“働き”を引き出す |
| 質駒 | 盤上の要(かなめ)を守る駒 | 失うと一気に形勢が傾く。交換は慎重に |
| 軽い手/重い手 | 形を崩さず次の手を残すのが軽い、負担が大きいのが重い | 攻め継続は軽く、受けは重く——が基本 |
| 位取り | 歩を突き伸ばして要所の“位”を確保 | 中盤の拠点づくり。角筋や飛車の通りと連動 |
| 厚み | 守攻に効く“手厚さ” | 形勢が悪くても厚みがあれば逆転の芽が生まれる |
| 逆王手 | 受けながら王手で切り返す着手 | 受けの最短反撃。“受けなし”を実現しやすい |
| 入玉 | 自陣を越えて敵陣に玉が到達すること | 点数勝負の局面へ。駒の点数管理が重要 |
駒の目安点(学習用の一例):歩=1/香=3/桂=4/銀=5/金=6/角=8/飛=9/と金=6/馬=12/龍=13(あくまで“目安”。状況で上下します)
【形勢判断の基礎】駒得・手番・玉の安全
形勢判断は「駒得(物量)」「手番(テンポ)」「玉の安全(耐久力)」の三本柱で整理します。三つのうち二つを確保できれば、多くの局面は戦いやすくなります。
逆に一つしか満たせないときは、満たしていない軸を一手で改善できる着手を探します。
- 駒得の実感例:自陣が薄くても、歩得+と金化で寄せの速度が上がるなら全体最適。点数目安で+2~3相当の得なら、多少の形の乱れを許容する価値があります。
- 手番の価値:連続王手や“利かし”で相手に受けを強要し続ければ、実質的に一手得が積み上がります。受けに回るときは確実に手番を取り返せる受け(たとえば合駒で次に攻め駒を握る等)を選びます。
- 玉の安全:囲いの堅さだけでなく“逃げ道”と“利きの遮断”まで含めて評価します。攻め駒を増やす前に、玉の呼吸スペース(脱出口)を一手で確保できないかを常に点検します。
ワンポイント演習:自分の次の手で「①駒得が進むか ②手番が維持できるか ③玉の安全が高まるか」を三つとも○×評価し、○が二つ以上つく手を優先候補にします。迷ったときほど有効です。
手順・手筋・切れ筋の違い(見分け方と訓練)
- 手筋:形が教えてくれる最適解。例:美濃囲いの金銀を“斜めから崩す”歩の突き捨て→銀打ち。まずは型の反復で視覚化します。
- 手順:実現までの順番。例:先に“利かし”を入れてから本命を指す。順番を取り違える“手順前後”は、同じ狙いでも価値が半減します。
- 切れ筋:読みに出口がない筋。途中で受けの一手や合駒を挟まれて頓挫する未来が見えたら、その読みは捨てます。
切れ筋チェックリスト
- 相手に空き王手・中合の手段が残っていないか。
- 主要攻め駒が遊び駒化しないか(働き続けられるか)。
- 最後に詰めろまたは利かしが残るか(残らないなら切れ筋の疑い)。
訓練法:詰将棋は“手筋の辞書”です。3~5手詰を毎日5題、同じテーマ(捨て駒、合駒、王手飛車など)で束ねて解くと、局面での“型”が瞬時に想起できるようになります。
【終盤の常套句】千日手、持将棋や捨て駒と早逃げ(適用条件の見極め)
捨て駒は“取らせて得をする”思想です。代表例は、
- ライン開通型:角・飛の利きを通すために歩や銀を捨てる。
- 玉形破壊型:合駒を強要して“質駒”を乱す(例:金を引きはがす)。
安全度の目安は、①取らせた後に必ず王手が続く、②最終図で詰めろまたは必至がかかる、の二条件です。
どちらかが欠ける捨て駒は、単なる“駒損”に終わる危険があります。
- 千日手とは、同一局面(手番・持ち駒・駒配置が同一)が4回出現したときの引き分けで、連続王手の千日手は攻め方の反則負けです。
- 持将棋とは、互いの玉が敵陣に入り詰みが見込めない場合の点数判定で、**飛・角=5点、金銀桂香歩=1点/合計27点以上で引き分け(不足側は負け)**です。
玉の早逃げは“寄せ合いのテンポをズラす”受けの最有力です。
- 早逃げの三条件:A) 逃げた先に広い逃走路がある/B) 相手の攻め駒の利きから外れる/C) 逃げた一手で相手の詰めろが消える。
- 悪い早逃げ:攻め合いで手抜き不可の詰めろを放置する早逃げ。これは“手番の自殺”になりがちです。
最後に、終盤は速度の競争です。毎手「これは詰めろか?」「受けは一つか?」を唱えるだけで、勝率が目に見えて変わります。
捨て駒・早逃げは“時間の売買”であることを忘れずに、速度計(詰めろ判定)を常にチェックしましょう。「
将棋用語の覚え方と学習ステップ
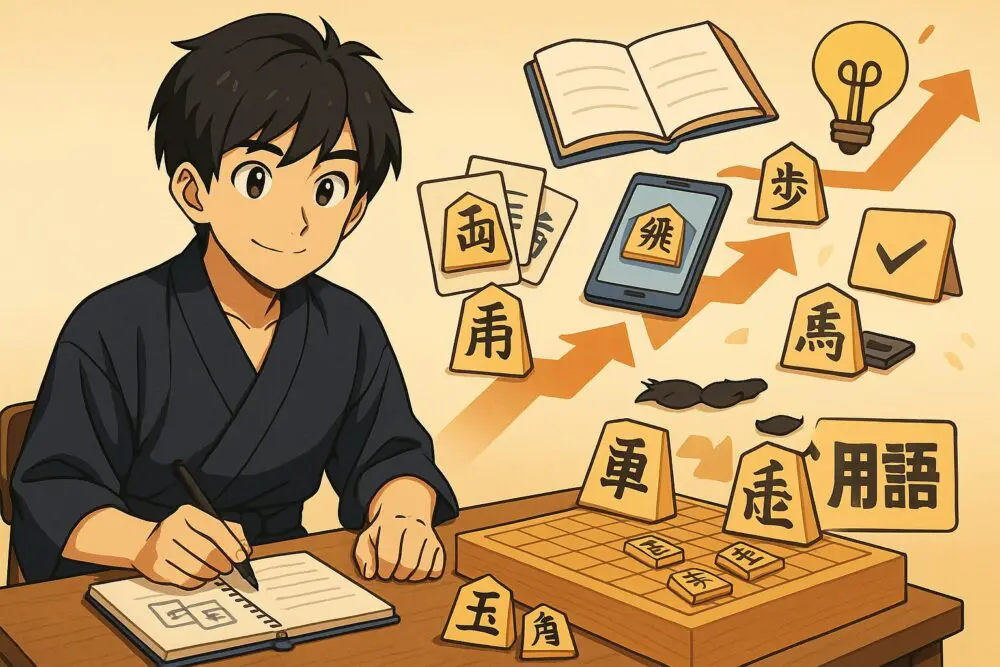
テーマ別・段階学習のすすめ
- 駒の名称と動き → 2) 基本動作(打つ・成る・王手) → 3) 局面・評価語(好手・疑問手・詰めろ) → 4) 解説語(手筋・手順・合駒)。
- 同一テーマを束ねて覚えると脳の引き出しが整理され、対局中の想起が速くなります。ここで重要なのは、用語を「丸暗記」ではなく使用場面とセットで記憶することです。
- 例えば「詰めろ」は“次に詰む脅し”という定義だけでなく、「中盤の攻め継続で相手に受けを強要したい時に使う」と紐付けておくと、実戦で即座に取り出せます。
4週間ロードマップ(例)
| 週 | テーマ | 具体目標 | 日々の練習(10〜15分) | 自己チェックの問い |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒と動き/基本動作 | 「成る・打つ・王手・合駒」を説明できる | 3手詰を3題、終局図の音読、「金銀の動き」シャドー盤練習 | この王手は“詰めろ”か?成らずの利点は? |
| 2 | 局面語・評価語 | 「好手・妙手・疑問手・悪手」の違いを言語化 | 観戦1局で良い手を3つメモ、感想戦で口に出す | 三軸(駒得・手番・玉の安全)のどれが良化? |
| 3 | 手筋と受け | 「突き捨て・叩き・中合・早逃げ」を例図で理解 | 同テーマ詰将棋5題、叩き→本命の“手順前後”練習 | 受けて手番を取り返せるか?利かしは残るか? |
| 4 | 仕上げ・運用 | 用語メモの統合と弱点補強 | 自戦1局を30秒/手で振り返り、用語で要約 | 次の対局で“口に出す用語”は何か? |
つまずきやすいポイントは三つに整理できます。第一に、範囲が広がりすぎること。週ごとに扱う語彙を限定し、他は“保留リスト”に逃がします。
第二に、例図の不足。言葉に図を1つずつ対応させ、A6サイズ程度のメモに図と一言をセットで記載します。第三に、アウトプット不足。
最低でも1日一回、観戦や詰将棋の後に「今日の学びを用語で三行まとめ」を書くと定着が飛躍的に高まります。
由来やエピソードで記憶に刻む
言葉に背景を付けると忘れにくくなります。例:「頓死(とんし)」は一瞬の油断で急に詰まされることを指し、囲碁由来とされる説もあります(諸説あり)。
この“油断が命取り”という物語をセットに覚えると、終盤での安全確認が習慣化します。
ほかにも、合駒は“線(利き)を合わせる駒”という語感からイメージしやすく、早逃げは“寄せ合いの速度をずらす受け”という時間の物語で記憶に残ります。
ミニ記憶法(作例)
- 語源フック:意味+短文の背景。「必至=どんな受けでも次に詰む→“運命の一手”」のように、感情語を添えます。
- 身体化:手を実際に盤上で動かしながら、声に出して読む。「利きを通す」「厚みを築く」を指差し+音読で結びつけると、視覚・聴覚・運動が同時に働きます。
- 二枚看板法:似た語を並置して覚える。例:「捨て駒=取らせて得/利かし=受けを強要して得」。カードを2枚並べ、差分一言を赤で書き足します。
さらに、間隔反復(Spaced Repetition)を用いると、忘却曲線の谷を効率よく越えられます。
初回→1日後→3日後→1週間後の復習タイミングで、毎回別の例図に差し替えると“定義の機械的反復”ではなく“概念の再利用”となり、応用力が伸びます。
似た用語の違いは表で一気に整理
| 似た用語 | 定義 | 相手の義務 | 例 |
|---|---|---|---|
| 詰み | 受けが一切ない終局 | なし(対局終了) | 最後の逃げ道も合駒も不可 |
| 詰めろ | 次に詰むと脅す手 | 受けが必要 | 「受けなければ詰む」状態 |
| 必至 | どんな受けをしても次に詰む | なし(実質的に勝負あり) | 受けても別筋で詰む |
| 好手/妙手 | まっすぐ良い手/一見損でも全体最適な手 | なし | 捨て駒で玉形破壊=妙手の典型 |
| 合駒/中合 | 王手の線に合わせる受け/途中のマスで受ける合い | 受けが必要 | 飛車筋に歩の中合で利きを遮断 |
| 利かし/脅し | 受けを強要し価値を得る/受けても価値が薄い | 受け(利かしのみ) | 受けて次の本命が通る=利かし |
| 受けなし/受けの一手 | 何を指しても効果がない/唯一残る受け | 受け(後者) | 「ここは受けの一手」→形勢の急所 |
ミニ確認問題(30秒)
- 「△4四歩が来ると▲同歩△同角で王手飛車の筋。ここで▲6八玉は早逃げか?」→“受けの一手が他にあるか”“次に利かしが残るか”で判定。
- 「▲6五歩が利かしになる条件は?」→受けを強要し、受け後に本命の手順が価値上昇すること。
覚えたらアウトプット習慣が決め手です。オンライン対局の感想戦で「ここは詰めろ」「この受けは切れ筋」「これは利かし」などと言葉にして確認しましょう。
最後に、学習ログとして一局三語メモ(今日得た用語×3+短い用例)を残すと、数週間後に自分の語彙の“伸び”が見える化します。
用語は“使ってこそ”自分の武器になります。
おすすめの将棋用語本2選

ここからはおすすめの将棋用語本を2冊紹介します。
実は将棋用語の本は数自体少ないのです。ここでは現代でも使えるものに絞って紹介します。
「観る将」もわかる将棋用語ガイド
『「観る将」もわかる将棋用語ガイド』は、青野照市著による細かく編纂された将棋用語に関する書籍です。
この本は、将棋の用語とその実際の使用を図面付きで分かりやすく解説し、将棋を実際にプレイする人だけでなく、観戦する人にとっても将棋の楽しさをさらに広げる内容となっています。
図面は各用語に2つずつ提供され、実際の指し手や実戦の進行を具体的かつ詳細に解説しています。
さらに、それにまつわる興味深いエピソードや背景情報も掲載されており、読者にとって将棋用語とその背後にあるストーリーをより理解しやすくしています。
近年では、将棋を実際にプレイせずに観戦するだけのファンの数が増えており、解説会や観戦イベントが非常に人気を博しています。
しかし、将棋用語を完全に理解していない「観る将」も多く、この状況が将棋コミュニティと新しいファンとの間にギャップを生んでいます。
この書籍は、そのギャップを埋めるための素晴らしいツールとなり、将棋用語を理解することで将棋の観戦が3倍おもしろくなると紹介されています。
また、将棋のプレイヤーやファンのコミュニティにおいて、言葉の壁を取り除くことで、より広範なコミュニケーションと交流を促進する助けともなっています。
青野照市『「観る将」もわかる将棋用語ガイド』創元社、2018、ISBN 978-4-422-75146-7。
将棋番組が10倍楽しくなる本
『将棋番組が10倍楽しくなる本』は、将棋ライターのアライ コウ氏によって書かれており、将棋の文化、歴史、専門用語、および戦法について解説されている本です。
この本は、将棋に詳しくない人でも将棋の番組を楽しめるようにすることを目的としています。特に、将棋に強くなるための本ではなく、将棋に詳しくなるための本です。
具体的な内容としては、どうやったらプロになれるのか、名人になるためにはどうすればいいのか、優勝賞金はいくらもらえるのかといった、将棋に関連するさまざまな話題がQ&A形式で解説されています。
さらに、この本には超人気女流棋士による描き下ろしコラムも収録されており、女流棋士の仕事の裏側についても覗くことができます。
また、「将棋文化検定」の受験者にとっては必読の1冊とされており、将棋文化や歴史について詳しく学ぶことができます。
肝心の将棋用語の数はそんなに多くないので、将棋用語だけでなく将棋について詳しくなりたい人向けの本になります。
『将棋番組が10倍楽しくなる本』(アライ コウ/ビジネス教育出版社、2019、ISBN 978-4-8283-0739-8)
まとめ
この記事では、初心者向け将棋用語の基礎と、対局での使い方・学習のコツについて解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 用語は「意味+使う場面+似た語との違い」で覚えるのが最短ルート。頻出10語・禁じ手・ミニ実戦譜で土台づくり。
- 形勢判断は「駒得・手番・玉の安全」の三本柱+「これは詰めろか?」の口癖化。王手と詰みの区別、受けの一手の重要性を最優先。
- 学習はテーマ束ね×間隔反復×アウトプット。4週間ロードマップ、声に出す読み、感想戦メモ(“一局三語”)で定着が跳ね上がる。
初心者向け将棋用語の習得では、用語を図・具体局面とセットで覚えることが重要なポイントとなります。
対局・観戦のたびに用語を口に出して確認し、三本柱チェックで手を評価、最後に短い感想戦メモを残す——この流れをぜひ実践してみてください。
さらに詳しく知りたい方は、はじめて将棋を指す!最初の一歩としての入門必読記事まとめもどうぞ。


