PR

・棋譜並べは「一局の流れ」「手筋」「終盤力」を一度に鍛えられる、意味のある練習法です。
・ルールを覚えた直後の初心者でも、序盤だけ・高速で並べる形なら十分効果があります。
・初段を目指すなら、実戦・詰将棋・定跡学習+棋譜並べの4本立てが理想で、棋譜並べは欠かせない要素の一つです。
棋譜並べ、興味はあるものの「何から始めればいいのか分からず」に困っていませんか?
ただ棋譜をなぞるだけの作業に思えて、本当に強くなるのか不安に感じている方も多いでしょう。
しかし棋譜並べは、プロも推奨する“三大上達法”の一つで、序盤の駒組みから終盤の勝ち切りまで、一局のストーリーごと学べる非常に効率的な勉強法です。
本記事では、棋譜並べの正しい意味と効果、棋力別の始めどきと具体的なやり方、棋譜の選び方、高速型/じっくり型の使い分け、さらに実戦・詰将棋・定跡学習とのバランスまで体系的に解説します。
この記事を読み終える頃には、自分に合った棋譜並べの取り入れ方が明確になり、大局観や思考速度が着実に伸びる実感を得られるはずです。
将棋の棋譜並べとは?まずは「意味」を整理する
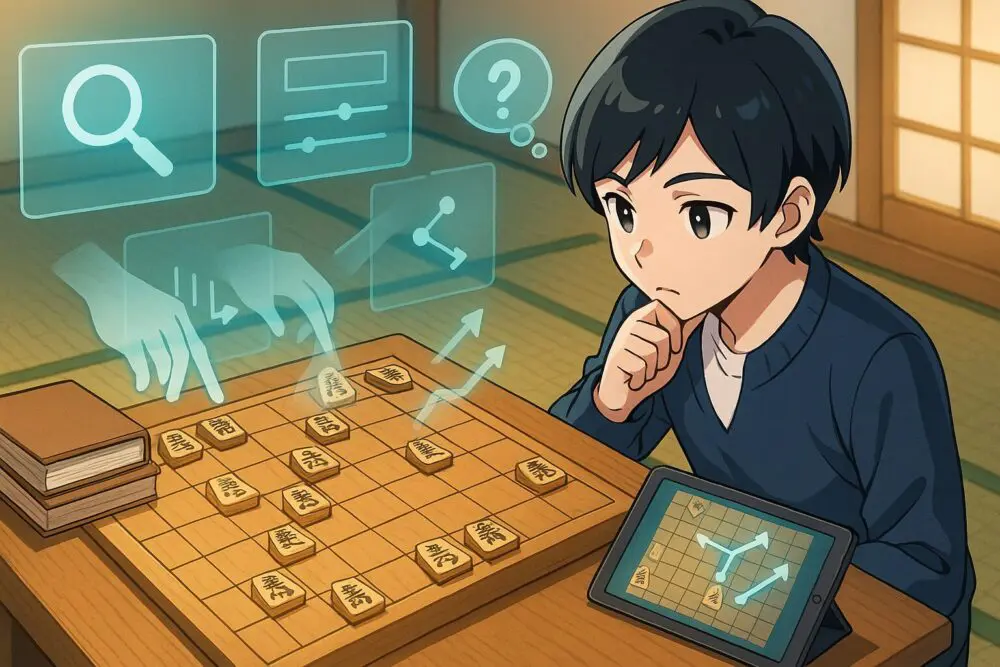
棋譜並べの基本的な定義
棋譜並べ(きふならべ)とは
過去に指された将棋の一局を、棋譜(指し手の記録)を見ながら、自分の手で最初から最後まで再現する練習方法です。
- 棋譜に書かれた符号どおりに駒を動かす
- 途中で出てくる局面を、自分なりに考えたり眺めたりする
- 時には途中図や解説を読みながら、なぜその手を指したのか理解を深める
この繰り返しによって、プロや上級者が実戦で使った「良い手順」に何度も触れられるのが特色です。
「三大上達法」の一つと言われる理由
日本将棋連盟のコラムなどでも、詰将棋・定跡・実戦と並び、棋譜並べは代表的な上達法として紹介されています。
- 詰将棋:終盤の読み・寄せの技術
- 定跡学習:序盤の型・方針
- 実戦:総合力・実戦感覚
- 棋譜並べ:一局の流れを通してそれらをまとめて鍛える
という位置づけで、特に「一局を通してのストーリー」を身につける点が、他の勉強法と違う強みです。
棋譜並べで鍛えられる力の全体像
棋譜並べで伸びるのは、次のような力です。
- 序盤から終盤までの流れ・大局観
- 駒の動きや将棋の符号への慣れ
- よく出てくる手筋・形のパターン
- 勝ち切る手順や、負けそうな局面からの粘り方
- 時間をかけすぎずに決断する思考速度
このように、棋譜並べは単なる「作業」ではなく、将棋の総合力を底上げする意味のある練習です。
棋譜並べで得られる主な5つの効果
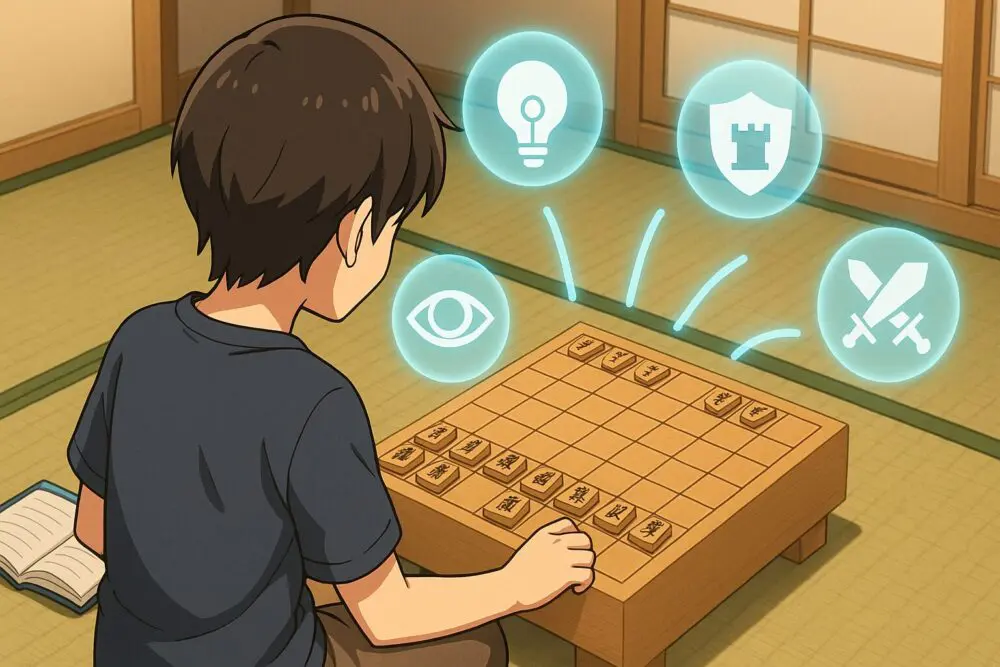
一局の流れと大局観が身につく
棋譜並べの大きなメリットは、一局全体の流れがつかめることです。
- 序盤:どのように駒を組み替え、戦いの準備をしているか
- 中盤:どこで主導権争いが始まり、どのような手筋で攻め・受けをしているか
- 終盤:リードを広げる手順、逆転の筋、詰みまでの寄せ
これを何局も体験すると、「この形になったら、そろそろ戦いが始まりそうだ」「この囲いなら、こう崩しにいくのが筋」といった、大局観が自然と身についてきます。
符号・手筋・定跡理解が自然と深まる
棋譜は、81マスのどこにどの駒が動いたかを表す「符号」で書かれています。
並べているうちに、この符号に自然と慣れ、将棋書籍やネットの解説も読みやすくなります。
さらに、
- 同じ戦型で繰り返し現れる「手筋」
- 多くの棋譜で共通して現れる「定跡の一部」
に何度も触れることで、考えなくても指が動くレベルで身についていきます。
指し手の幅と終盤力・勝ち切る力が上がる
棋譜並べをしていると、「自分だったらこう指していただろうが、実際は別の手が指されている」という場面に何度も出会います。
そのたびに、
- 「なぜ自分の候補手ではなく、実戦の手が選ばれているのか」
- 「この手にはどんな狙いがあったのか」
を考えることで、指し手の引き出しが増えていきます。
終盤についても、プロや上級者の勝ち切り方・逆転の狙いを何度もなぞることで、実戦での「詰めろ」「受け」「反撃」のバランス感覚が磨かれます。
棋力別|いつから棋譜並べを始めるべきか

ルール習得直後〜初心者(10級前後)の場合
結論から言うと、初心者でも棋譜並べは意味があります。
- 駒の動きと符号に慣れる
- よく出てくる基本的な形を「目」で覚える
- 序盤の駒組みのイメージをつかむ
といった効果が期待できます。
ただし、最初から最後まで完璧に並べる必要はありません。
- 序盤10〜20手だけ並べる
- 途中で局面が崩れたら、一度リセットしてやり直す
この程度でも、十分に「筋の良さ」を育てる効果があります。
級位者(9〜1級)の場合
ある程度対局経験があり、自分の得意戦法やよく指す戦型が見えてきたら、棋譜並べの効果は一気に高まります。
- 自分の戦型のプロの棋譜を題材にする
- 1局を15〜30分で並べきることを目標にする
- できれば同じ棋譜を複数回並べて、流れを身体で覚える
といった取り入れ方がおすすめです。
初段を目指す人にとっての「必要度」
棋譜並べだけで初段に到達するのは現実的ではありませんが、
初段を目指す過程で「かなり重要なピース」であることは確かです。
- 実戦
- 詰将棋
- 定跡・手筋の勉強
- 棋譜並べ
これらをバランス良く回すことで、初段レベルに必要な総合力が整っていきます。
特に、一局の流れや終盤の勝ち切り方は、棋譜並べで磨かれやすい部分です。
棋譜並べの基本的なやり方【手順と時間の目安】
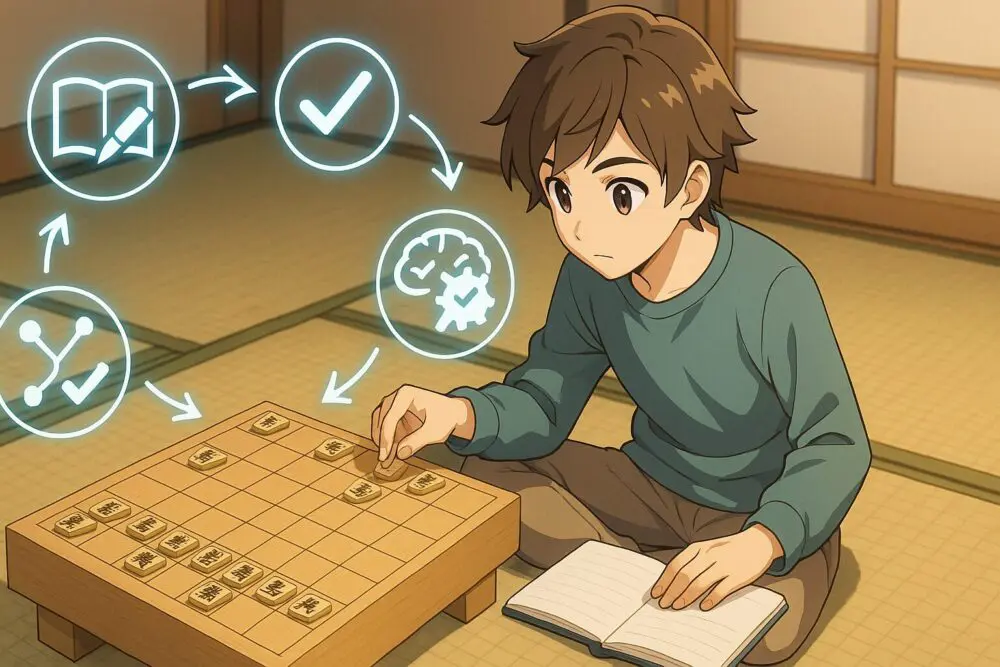
【準備するもの】盤駒かアプリか?
理想を言えば、本物の盤駒を使うのがおすすめです。
- 手で駒を動かすことで、感覚的に記憶に残りやすい
- 実戦に近い姿勢・視野で局面を眺められる
一方で、スマホアプリやPCソフトでの棋譜並べも、手軽さという点では大きなメリットがあります。
- 通勤時間やスキマ時間に1局だけ並べる
- 間違えたときにすぐ局面を戻せる
など、継続しやすさを重視するならデジタルも十分選択肢です。
まずは「続けやすい方法」で始め、慣れてきたら盤駒でじっくり、と使い分けるのが現実的です。
初心者は「序盤だけ」でもOKな理由
初心者が最初から最後まで完璧に並べようとすると、
- 符号に慣れていない
- 終盤の難しい手が理解しづらい
といった理由で挫折しやすくなります。
そこでおすすめなのが、
- 序盤10〜20手だけ並べる
- できれば同じ局面を何度か繰り返し並べる
というシンプルな方法です。
序盤に絞ることで、
- 駒の基本的な配置
- 囲いの形
- 開戦前の理想的な形
といった「土台」がしっかりしてきます。これは、中盤・終盤の力を支える重要な基礎になります。
高速棋譜並べとじっくり型の使い分け
棋譜並べには、大きく分けて2つのスタイルがあります。
- 高速棋譜並べ
- 1局10分以内を目安に、できるだけ速く並べる
- 手の意味はあまり深く考えず、「型」を体に入れるイメージ
- じっくり型棋譜並べ
- 1局15〜30分程度かけて、要所要所で立ち止まり考える
- 「自分なら何を指すか」「実戦の手との差」を意識する
初めての棋譜はじっくり型で、慣れてきたら同じ棋譜を高速で何度も並べるという組み合わせが、理解と定着の両方を狙える形です。
棋譜の選び方|失敗しない4つのポイント

自分の得意戦法・よく指す戦型の棋譜を選ぶ
棋譜選びで一番大切なのは、自分の戦型に近い将棋を選ぶことです。
- 四間飛車党なら、四間飛車の名局
- 矢倉を多く指すなら、矢倉の将棋
- 相掛かりや角換わりが多い人は、その戦型の棋譜
自分の実戦でよく出てくる形を題材にすることで、
- 「自分もこの形で困っていた」
- 「ここでこう指せば良かったのか」
といった気付きが多くなり、対局への反映も早くなります。
好きな棋士の将棋を題材にするメリット
好きな棋士や目標とするスタイルがある場合、その棋譜を集中的に並べる方法も有効です。
- モチベーションが高く保てる
- その棋士の「考え方」や「局面の好み」が見えてくる
- 自分のスタイルに取り入れたい要素が見つかる
楽しさがあると継続しやすく、それ自体が大きなメリットになります。
解説付きの観戦記・自戦記を優先する
解説が付いた観戦記や自戦記の棋譜は、棋譜並べの教材として非常に優秀です。
- 「この手にはこういう狙いがある」
- 「別の候補手もあったが、こちらを選んだ理由」
- 「この手が悪く、形勢が傾いた」
といった情報が書かれているため、自分一人では気づきにくいポイントまで学べます。
解説のない棋譜をおすすめしない理由
解説のない棋譜は、上級者には良い教材になることもありますが、
初心者〜級位者にはおすすめしづらい側面があります。
- 良い手と悪い手の区別がつきにくい
- なぜその手が指されたのか分からず、「写経」で終わりやすい
- 結果的に、誤った理解のまま覚えてしまう危険もある
「最初のうちは、解説付き」を基本ルールにしておくと、
学習効率が大きく変わってきます。
棋譜並べの成功の鍵|量・思考速度・他勉強法とのバランス
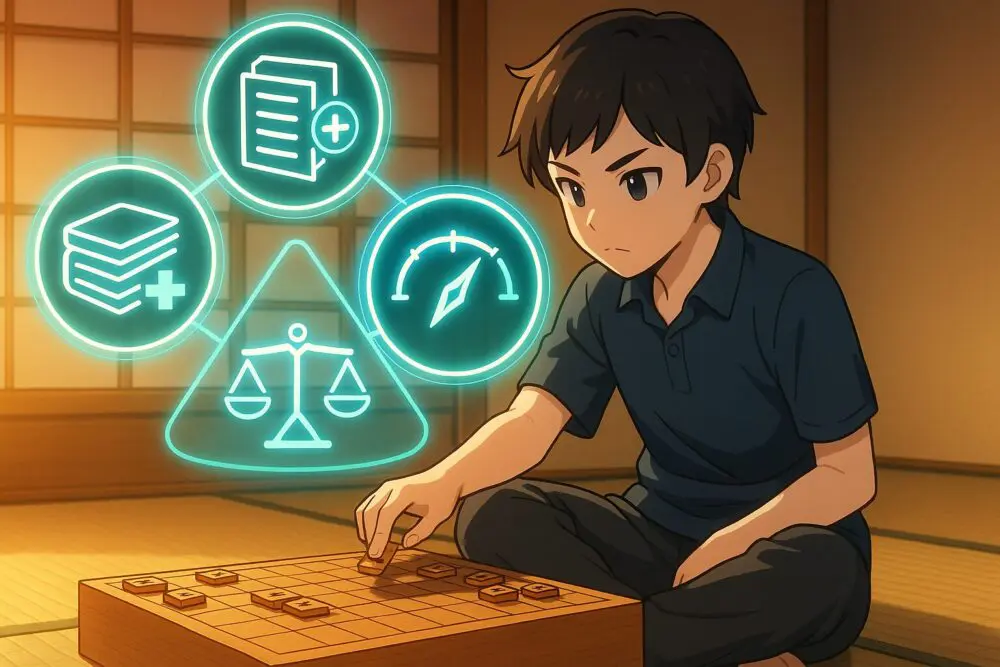
1局にかける時間と回数の目安
一般的な目安として、次のように考えるとバランスが良くなります。
- じっくり型:1局15〜30分
- 高速型:1局10分以内
また、効果を実感しやすいのは、
- 同じ棋譜を10〜30回ほど繰り返す
- 合計で50〜100局程度の棋譜を並べてみる
といったボリューム感です。
思考速度が上がる理由と「大量に並べる」意味
棋譜並べを繰り返すと、よく出てくる形や手筋に対して、
この形なら、だいたいこのあたりの手が有力」
といった感覚が、ほとんど反射的に出てくるようになります。
その結果、
- 持ち時間の短い将棋での判断が速くなる
- 中盤の難しい局面で迷いすぎない
- 終盤で残り時間を確保しやすくなる
といった形で、思考速度の向上が勝率に直結していきます。
実戦・詰将棋・定跡学習とのバランス
棋譜並べは優れた勉強法ですが、それだけに偏るとバランスを欠きます。
おすすめの比率イメージは、
- 実戦:40〜50%
- 詰将棋:20〜30%
- 定跡・手筋:10〜20%
- 棋譜並べ:10〜30%
くらいです(あくまで一つの目安です)。
- 対局で「課題」を見つける
- 詰将棋と定跡・手筋で「局面ごとの力」を鍛える
- 棋譜並べで「一局の流れと大局観」を養う
という役割分担を意識すると、勉強全体の効率が上がります。
よくある質問(FAQ)
Q 棋譜並べとはどんな練習法ですか?
過去に指された一局を棋譜どおりに最初から最後まで自分の手で再現し、途中局面を考えたり解説を読みながら理解を深める練習法です。
Q 棋譜並べで鍛えられる力は何ですか?
序盤から終盤までの流れや大局観、符号への慣れ、手筋や形のパターン、勝ち切る手順や粘り方、時間をかけすぎない思考速度などが総合的に鍛えられます。
Q 初心者が始めるときのポイントは何ですか?
最初から最後まで完璧に並べようとせず、序盤10〜20手だけを並べたり局面が崩れたらリセットしてやり直す程度でも十分な効果があるとされています。
Q 級位者は棋譜並べをどう活用すべきですか?
自分の得意戦法やよく指す戦型のプロの棋譜を題材にし、1局を15〜30分で並べきることを目標にしながら、同じ棋譜を複数回並べて流れを身体で覚えると良いとされています。
Q 盤駒とアプリではどちらで並べるべきですか?
理想は本物の盤駒で手で駒を動かすことですが、通勤時間などに手軽にできて局面を戻しやすいアプリやPCソフトにもメリットがあり、まずは続けやすい方法で始めて慣れたら盤駒でじっくり行うとされています。
Q 高速型とじっくり型の違いは何ですか?
高速棋譜並べは1局10分以内で手の意味を深く考えず型を体に入れるイメージで、じっくり型は1局15〜30分かけて要所で立ち止まり自分の候補手と実戦の手を比較しながら考えるスタイルです。
Q どんな棋譜を題材に選ぶと効果的ですか?
自分の得意戦法やよく指す戦型の将棋や好きな棋士の将棋を選び、特に狙いや候補手の説明が書かれた解説付きの観戦記・自戦記の棋譜を優先すると学びやすいとされています。
Q どのくらいの量と回数を並べると良いですか?
じっくり型は1局15〜30分、高速型は1局10分以内を目安とし、同じ棋譜を10〜30回ほど繰り返し、合計で50〜100局程度並べてみると効果を実感しやすいとされています。
Q 他の勉強法とのバランスはどう取りますか?
実戦を40〜50%、詰将棋を20〜30%、定跡・手筋を10〜20%、棋譜並べを10〜30%程度とする一つの目安が示されており、一局の流れや終盤の勝ち切り方を棋譜並べで養う役割分担が提案されています。
まとめ
この記事では、将棋の「棋譜並べ」の意味と効果、そして具体的な始め方や取り入れ方について解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 棋譜並べとは、過去の対局を棋譜どおりに最初から最後まで再現し、一局の流れや大局観・手筋・終盤力など将棋の総合力を底上げする練習法である。
- 棋力に応じて「序盤だけ並べる」「じっくり型と高速型を使い分ける」「自分の戦型・好きな棋士・解説付きの棋譜を選ぶ」といった工夫をすることで、初心者〜初段を目指す人まで高い学習効果が得られる。
- 棋譜並べは、実戦・詰将棋・定跡学習とバランスよく組み合わせ、大量に繰り返すことで思考速度が上がり、一局のストーリーや勝ち切る技術が身につきやすくなる。
棋譜並べでは、「自分の戦型に合った解説付きの棋譜を選び、じっくり型と高速型を織り交ぜながら量をこなすこと」が重要なポイントとなります。
将棋の勉強では、ぜひこの記事でご紹介したポイントを押さえて、日々のトレーニングに無理のない形で棋譜並べを取り入れてみてください。
将棋初段になる勉強法を詳しく知りたい方は【将棋アマチュア初段を目指す】効果的な将棋勉強法と本まとめもどうぞ

