PR

将棋駒、どれを選べば失敗しないんだろう。価格や製法が多すぎて迷っていませんか?
安さだけで決めると滑りや可読性、耐久で後悔しがちです。
本記事は、実用品であり伝統工芸でもある駒の価値を、製法(押し・書き・彫・彫埋・盛上)、材(本黄楊ほか)、書体、価格要因、店頭チェック、メンテまで体系的に解説。
初心者の最適解から本格派の選び方、保管のコツ、段階的なアップグレードの道筋まで網羅します。
この記事を読めば“指し味と鑑賞性の両立”を迷いなく実現し、長く愛せる一組に最短距離で辿り着けます。結論はあなたの優先軸を定め、盤と手に合う駒を理性と感性の両輪で選びましょう。
将棋駒は“道具”以上の価値がある

実用品であり、同時に伝統工芸
将棋駒は盤上で正確に動かせる機能が第一ですが、素材の選定、木地の乾燥、書体の運筆や漆の厚みなどに高度な職人技が宿ります。
毎日使う茶碗に陶芸の美意識が宿るのと同じで、駒は「使ってこそ味が出る工芸」。指すたびに手に馴染み、色艶が深まり、道具の域を超えた愛着が蓄積していきます。
加えて、厚みや角度の僅かな誤差を抑える寸法管理、重心の安定を生む面取りの加減も品質を左右します。摺り漆・拭き漆の仕上げは手汗と呼応して艶を深め、使用と休息のサイクルが美観を育てます。
欠けや漆の剥がれは手当てが可能で、世代を超えて受け継げる「修理しながら使う文化」も魅力です。
製法の違いが生む手触りと表情
同じ木地でも、押し(スタンプ)、書き(書筆)、彫(彫刻)、彫埋(彫って漆を埋める)、盛上(厚い漆で線を盛り上げる)では触感と見え方が大きく変わります。
彫りは凹凸が生む指止まりの良さ、盛上は漆線の陰影の豊かさが魅力。駒を摘まむ瞬間の滑り具合や、盤に置いたときの音色までもが製法の個性を語ります。
押しは軽快で均一な反面、長年の摩擦で退色しやすく、書きは筆致の“揺らぎ”が味になります。彫は線が磨滅しにくく実戦向き、彫埋は面の整いが照明下でも字が途切れず見やすい。
盛上は経年で層が締まり、斜光で立体感が際立ちます。厚みと面取りの差は音色にも影響し、乾いた「コトン」か張りのある「パチン」かの違いを生みます。
同じ「歩」でも別物の味わい
歩一枚でも、木目の向き、厚み、角の面取り(面の取り方)、書体の骨格で印象が一変します。黄楊材は密度が高く、手汗を吸って艶が増す一方、樹脂は軽快で扱いやすい。
視認性の高い書体は実戦で疲れにくく、線に勢いがある書体は気分まで引き締めます。小さな差が蓄積し、所有満足と指し味の記憶を形づくります。
さらに、駒の背の反り具合や台形の勾配、中心部の厚みの取り方は摘まみやすさに直結します。裏字や成り字の品位、朱漆の発色は盤上の緊張感を整え、照明の色温度によっても見え方が変わります。
盤のマス目サイズとの相性や手の大きさとのバランスまで含めて一枚の「歩」を吟味すると、選択の精度が上がります。
【基礎知識】将棋駒の種類と特徴|

製法は「押し・書き・彫・彫埋・盛上」に大別
駒字の表現方法は大きく五系統です。押しは量産向きで均一、書きは筆致の生々しさ、彫は線が長持ち、彫埋は面の整いと陰影、盛上は立体感と格調が際立ちます。
どれが上位という序列ではなく、用途・予算・好みの三要素で最適解が変わります。まず分類を押さえると、候補の絞り込みが一気に楽になります。
さらに、各製法は工程と管理点が異なります。押しは転写精度と耐摩耗インクがポイントで、扱いやすさと均一性が武器です。
書きは下書きの取り方と運筆の切れで生命感が決まり、光源によって表情が豊かに変化します。彫は刃物の角度と深さが重要で、指の腹に触れる凹みが自然なブレーキとなり、早差しでも取り違えを防ぎます。
彫埋は彫った谷に漆を均一に回す難度が高く、面の整いが視認性を底上げします。盛上は塗り・乾燥・研ぎを繰り返し層を立てるため、立体線のエッジが揃うほど格調が増し、角度による陰影の豊かさが鑑賞性を高めます。
価格は手間と工程の深さにおおむね比例
価格帯は木地の質(材、杢、含水率(がんすいりつ)管理)、字入れの難度、研ぎや仕上げ回数に連動します。
押し・書きは入門向けの良心価格、彫は中位で耐久と実用の均衡、彫埋(ほりうめ)は高精度の加工と漆仕事、盛上(もりあげ)は繰り返しの乾燥・研ぎ出しに時間を要し、工芸的価値が反映されます。
値札は“時間と技術の履歴”の可視化と考えると納得感が生まれます。
加えて、木地等級(柾目(まさめ)の通りや板目(いため)の表情、玉杢(たまもく)などの希少杢)、原木の産地や枯らし年数、歩から大駒に至る文字幅の安定度などもコストに影響します。
手彫は駒種ごとに工程差が出やすく、角・飛のような画数の多い駒は調整に時間を要します。漆は乾燥環境の管理が品質を左右し、湿度・温度を守った“寝かせ”の回数が多いほど単価に反映されます。
作家性や銘の評価、制作本数の希少性が加わると、同等の仕様でも価格が離れることがありますが、これは将来的な修理対応や品質保証の範囲にも連動します。
価格決定の主因(要点)
- 木地等級(柾目の通り・板目の表情・玉杢など希少杢)
- 枯らし年数と含水率管理(反り・割れの予防)
- 製法の工程数と手加工比率(押し→書き→彫→彫埋→盛上)
- 漆の塗り重ね回数と乾燥環境管理(“寝かせ”の回数)
- 駒師の銘・制作本数・作家性(将来の修理可否)
- 付帯価値(鑑別書・保証・アフターサービス)
全体像を把握して迷いなく選ぶ
自分の優先は「視認性/手触り/鑑賞性」のどれかを軸にすると迷いにくくなります。
大会・教室など移動が多い方は軽量で均質な押し・樹脂系、日々の実戦重視は機械彫〜手彫、所有満足と工芸性を求めるなら彫埋・盛上へ。
いずれも盤との相性(色・音)で満足度が変わるため、可能なら盤と並べて見比べるのが最短ルートです。判断の精度を高めるには、使用環境とメンテナンス許容度も加味します。
道場や大会中心なら耐摩耗性と視認性を、家庭対局と鑑賞を兼ねるなら陰影や杢目の味わいを重視すると失敗が減ります。
サイズ(王将の高さや厚み)と手の大きさ、盤の材と色(新榧・桂・プラ盤)とのコントラスト、置いた時の音色まで含めて“体験”で選ぶのがコツです。
購入前に店頭や写真で斜光の状態を確認し、裏字の品位、左右の払いの勢い、歩以外の駒でも骨格が崩れていないかを見れば、長く愛せる一組に近づきます。
用途別おすすめ(目安)
| 用途 | 製法の目安 | 主な材 | 注視ポイント |
|---|---|---|---|
| 家庭練習・初心者 | 押し/機械彫 | 樹脂/シャム黄楊 | 視認性・扱いやすさ・耐久 |
| 教室・出張対局 | 押し/機械彫 | 樹脂/シャム黄楊 | 軽量・均一・耐候性・収納 |
| 対局会・大会 | 機械彫/手彫 | シャム/本黄楊 | 指止まり・可読性・音色 |
| 鑑賞も楽しむ | 彫埋/盛上 | 本黄楊 | 陰影・杢目・書体の調和 |
製法別の比較(要点のみ)
| 製法 | 文字表現 | 触感/視認性 | 耐久 | 価格傾向 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 押し | スタンプ | 均一で見やすい | △ | 低 | 低予算・持ち運び |
| 書き | 直書き | 筆致の味 | △〜◯ | 低〜中 | 雰囲気重視 |
| 彫 | 凹線 | 指止まり良 | ◯ | 中 | 実用・長期 |
| 彫埋 | 彫+漆埋め | 面整い・陰影 | ◯〜◎ | 中〜高 | 実用+鑑賞 |
| 盛上 | 厚漆立体 | 立体感・格調 | ◎ | 高 | 鑑賞・晴れ |
上の比較表は要点の圧縮版です。実際の選定では、製法ごとの音色や光の反射、指の腹に当たる感触の違いが満足度を左右します。
机上で数枚を軽く滑らせ、止まる位置の安定や手汗での滑り具合を確かめると、使用後のギャップが小さくなります。
反りや歪みは平らな面に裏返して置き、四隅の浮きやすさを目視すれば簡易チェックが可能です。
材質・書体・デザインの違いを楽しむ|
本黄楊(ほんつげ)の王道の指し味と育つ艶
本黄楊(ほんつげ)は緻密で粘りがあり、指先にしっとり吸いつく独特の手触りです。使うほど微細な傷が艶へと転じ、色味も飴色へ熟成します。盤に置くと「コトン」と芯のある音が響き、集中を助けます。
投資感覚で長く付き合える材で、初心者が最初から選んでも、数年後に“買い替えたい理由がない”と感じやすい素材です。
さらに、含水率の安定や木取り(柾目中心か板目か)によって反りにくさが変わり、角の面取りの角度と幅は摘まみやすさと音色に影響します。
日々の乾拭きと、季節の湿度管理だけでも艶は確実に育ち、手脂が均一に広がることで色調が落ち着いていきます。
シャム黄楊など他材と比べると、重心の落ち着きと“指の腹に吸い付く感じ”が際立ち、長手数の将棋ほど差が実感しやすいのが本黄楊の強みです。
書体は駒の「顔」【可読性と印象を左右】

同じ駒でも、菱湖系(りょうこけい)は骨太で堂々、錦旗(きんき)は端正で大会映え、水無瀬(みなせ)は流麗(りゅうれい)、源兵衛清安(げんべえきよやす)は古雅(こが)で柔らかい印象です。
読み違いを防ぐには線幅の均整や余白設計が重要で、実戦では瞬間認識のしやすさが効率を左右します。第一印象だけでなく、長時間見続けても疲れにくいかを基準に、顔つきの“相性”で選びましょう。
加えて、字面の重心(縦に締まっているか、横に広がるか)、払いの伸びや止めのキレ、裏字との整合も評価点です。
照明が強い会場ではコントラストが強く出る書体が有利で、自宅の暖色照明では線が太すぎない方が目に優しい傾向があります。
店頭では「歩・香・角・飛」の4枚を並べ、一歩引いて見たときの識別しやすさと、近寄って見たときの線の呼吸をセットで確認すると失敗が減ります。
主要書体の比較(目安)
| 書体 | 印象 | 可読性(瞬間/長時間) | 向き |
|---|---|---|---|
| 菱湖(りょうこ) | 骨太・堂々 | 瞬間◎ / 長時間◯ | 競技・対局映え |
| 錦旗(きんき) | 端正・正則 | 瞬間◯ / 長時間◎ | 大会・教育現場 |
| 水無瀬(みなせ) | 流麗・のびやか | 瞬間◯ / 長時間◎ | 家庭対局・鑑賞 |
| 源兵衛清安(げんべえきよやす) | 古雅・柔和 | 瞬間◯ / 長時間◯ | 鑑賞・落ち着き重視 |
漆の陰影と木目の表情が生む工芸性
漆は光を柔らかく受け、斜光で線に立体感が生まれます。彫埋や盛上は、黒の深みと木地の金色が対比して、写真では拾いきれない陰影の豊かさが現れます。
杢目(虎杢(とらもく)・柾目など)も印象を左右し、派手すぎない杢は実戦時の視認性と鑑賞性のバランスが良好です。“盤上のミニマル工芸”として、素材×書体×漆の調和を味わえます。
さらに、黒漆と朱漆(しゅううるし)の使い分けや、艶を抑えた仕上げと鏡面寄りの仕上げで表情は大きく変わります。
盤材の色(新榧・桂・プラ盤)とのコントラストも陰影の見え方に直結し、明るい盤にはやや濃い字色、暗めの盤には抜けの良い線幅が好適です。
お手入れは柔らかい布での乾拭きが基本で、ワックス類は避け、直射日光と急激な湿温変化を遠ざけるだけで、漆の冴えと木目の立ち上がりを長く楽しめます。
【初心者向け】入門用駒の選び方

源平色分けで直感的に覚える
赤と黒で敵味方や成りの向きを把握しやすい源平配色は、はじめての方の学習曲線を穏やかにします。
駒の上下や裏表を迷いにくく、対局のリズムが崩れません。視認性が高いぶん、正しい指し手に意識を割けるため、定跡学習より前の段階で「動きの型」を身体に入れる助けになります。
教室や親子対局にも相性抜群です。さらに、色の明度差が大きいほど遠目からの識別が容易で、子どもやご高齢の方でも疲れにくい利点があります。
最初は源平で運用し、慣れてきたら通常配色の駒に段階移行する「二段階学習」にすると、記号(色)依存から形状・書体認識へ自然に橋渡しできます。
大会参加を視野に入れる方は、源平と通常の両方に触れておくと移行時のギャップが最小化できます。
迷ったらシャム黄楊の機械彫が最適解
価格と実用のバランスを重視するなら、シャム黄楊の機械彫が堅実です。密度が十分で、指し味は軽快すぎず、彫り線が摩耗に強いので長く使えます。
書体の選択肢も多く、盤との色相差が適度に出るため視認性が高い点も魅力です。将来的に上位を目指す場合でも、練習用・持ち出し用として無駄になりません。
加えて、機械彫は個体差が小さくセット内の統一感が高いため、初心者が形・大きさ・重心の違いで混乱しにくいという利点があります。
選ぶ際は、角の面取りが均一であるか、裏字の濃さが揃っているか、数枚を盤上で滑らせたときの止まり具合が安定しているかを確認しましょう。
これらが満たされていれば、毎日の練習から対局会まで不満の少ない一組になります。
店頭チェック(簡易)
- 角の面取りが四隅とも均一で欠けがない
- 裏字の濃さ・筆圧が揃い、にじみや欠けがない
- 数枚を盤上で軽く滑らせ、止まり方が安定している
- 反り・ねじれがない(裏返して四隅の浮きを確認)
- 号数・厚みが手の大きさに合う(摘まみやすさ)
- 手持ちの盤との色差・音色が好みか
持ち運び重視なら押し駒や樹脂製
教室・サークル・旅先での対局が多いなら、軽量で割れにくい樹脂製や押し駒が便利です。均一な仕上がりで枚数チェックがしやすく、雨天や温湿度の変化にも強いのが実用的。
盤を含むセットで選ぶ場合は、駒の厚みと盤のマス目サイズの相性(詰まりすぎないか)を確認しましょう。収納ケースの保護性も快適さに直結します。
さらに、マグネット内蔵タイプは移動中に並び替えが崩れにくく、カフェや移動体験でも実用的です。
反面、磁力が強すぎると着手が重く感じるため、数枚でテストして“吸い付き過ぎない”個体を選ぶのがコツです。
ケースは角保護の緩衝材と湿度対策(乾燥剤の小袋)があると安心で、出し入れ頻度が高い方はファスナー式やハードケースが長持ちします。
【本格派向け】高級駒の世界

彫埋・盛上は“駒の形をした工芸作品”
彫埋は彫りの正確さと漆の均一な埋めが試され、面の整いと落ち着いた陰影が身上です。盛上は厚い漆を幾度も重ね、乾かし、研ぎ、線を立体的に起こします。
どちらも盤上での視認性に寄与しつつ、手にした瞬間の高揚感は別格。実用と鑑賞が高い次元で両立し、所有体験そのものが趣味になります。
さらに、彫埋は面が静かに光を返すため長時間の対局でも目が疲れにくく、盛上は斜光で線が浮き立つことで瞬間識別性が高まります。
仕上げの研ぎ出しや呂色の精度、角の面取りの均一さ、線のエッジの立ち具合は、写真では伝わりにくい“格”の差として表れます。
注文制作では木地の杢と書体の相性、裏字の品位、塗り重ねのポリシーまで確認できると、完成時の満足度が安定します。
産地・工房・駒師名・書体表示を確認
高級駒は製作者情報が価値の一部です。産地(薩摩黄楊など木地由来)、工房の仕立て、駒師の銘、採用書体の系統まで表示を確認しましょう。
作例写真の角度や斜光の有無、裏字(成り字)の品位、歩以外の駒で線の安定感が保たれているかも重要です。納得のいく情報開示は、良い作り手の誠実さの表れです。
加えて、木地等級(柾目の通り・板目の表情・玉杢の有無)、枯らし年数や含水率管理、仕上げの艶感(控えめか鏡面寄りか)、本漆か合成塗料かの表記、号数と厚みの実測値、付属の鑑別書や保証範囲まで目を通すと安心です。
店頭では数枚を並べ、正面・斜め・俯瞰で観察し、音色・手離れ・光の抜けを確認する「三点チェック」を行うと、実使用時のギャップが小さくなります。
購入前チェックリスト(要点)
- 表示:産地・木地等級・枯らし年数・仕上げ種別(本漆/合成)
- 書体:系統・裏字の品位・歩以外の安定感
- 物性:反り/ねじれ・重量バラつき・面取りの連続性
- 付帯:鑑別書・保証・修理可否・納期と返品条件
- 体験:音色・斜光での陰影・1m/30cmテストでの視認性
保管は桐箱+駒袋、環境変化を避ける
高密度の黄楊ほど環境変化に敏感です。
桐箱+駒袋で直射日光と急激な温湿度変化を避け、使った後は乾拭きで皮脂をならし、湿気が強い日は箱を少し開けて呼吸させます。
防虫香は直接接触させず、強い香りは漆に移ることがあるため控えめに。修理は自己処置を避け、漆の割れや欠けは専門店へ相談すると安心です。
さらに、梅雨時や真夏は乾燥剤を入れ替え、冬場の過乾燥では駒袋だけで寝かせて急な乾き過ぎを防ぎます。水濡れ時は擦らず押し当てて吸水し、直射日光やドライヤーで急乾燥させないことが肝要です。
オイル類・艶出し剤は漆層を曇らせることがあるため避け、保管場所は温度20℃前後・湿度60〜70%の範囲を目安に“緩やかに”守ると、艶は自然に育ちます。
将棋駒を深く味わうためのガイド
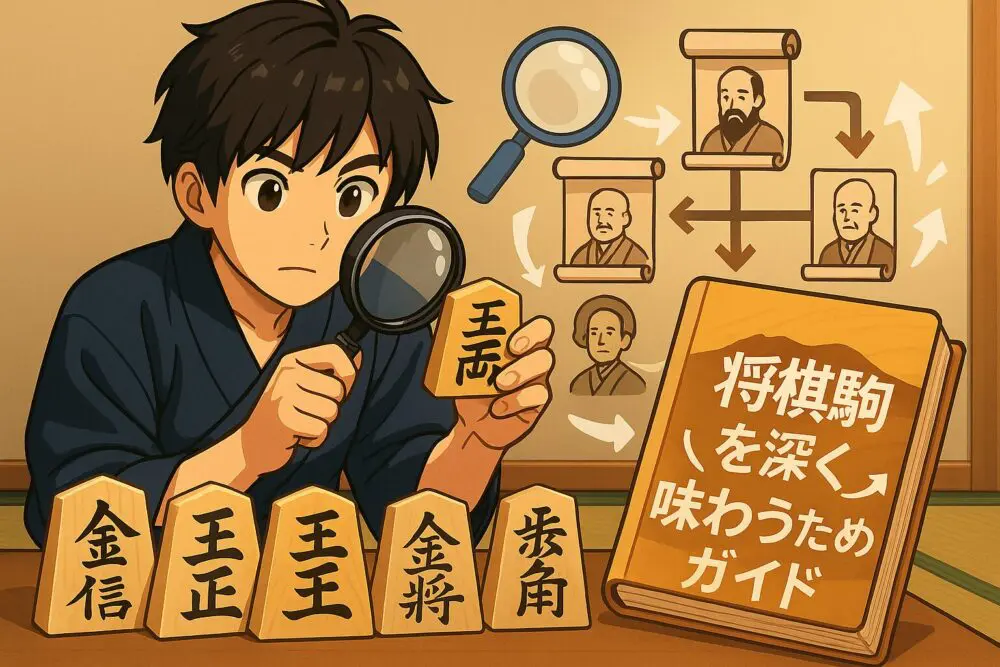
書体と名駒師の系譜解説
四大書体と称される菱湖・錦旗・水無瀬・源兵衛清安は、それぞれ成立背景と美意識が異なります。菱湖は骨格の太さと堂々たる風格が特徴で、払いの伸びやハネの力感が盤面全体に威厳を与えます。
錦旗はマス目に対して重心が安定し、線幅と余白の比が整っているため競技向きです。水無瀬は筆致の流れが美しく、字面の呼吸が軽やかで長時間見ていても疲れにくい書体です。
源兵衛清安は古筆の余情を残し、丸みのある骨格と抑えた線の強弱が柔和な印象を生みます。
同じ書体でも駒師により骨格や勢いが変わり、刃物の入れ方や漆線の立ち上げ、収筆の粋(いき)、面取りの見切りで個性が立ちます。
結果として、線の切れ味、余白設計、字面の呼吸感が“銘”として語られ、所有者の審美眼と実用の両面で評価されます。
盤材や照明環境との相性も無視できず、明るい新榧には骨太な菱湖や濃色の錦旗が映え、暖色照明の室内では水無瀬や源兵衛清安のしなやかさが馴染みます。
号数や厚みとの釣り合いも書体選びの一部で、同じ書体でも小振りな駒では線が詰み、大ぶりな駒では余白が間延びして見えることがあるため、実寸での確認が有効です。
鑑賞ポイントと保管・メンテナンス|
鑑賞時は斜光を当て、線の厚みや面の整い、漆の均質性、角の面取りの精度を見ます。
具体的には、自然光または演色性の高い白色LEDを45度前後の角度から当て、線のエッジが途切れず立ち上がっているか、谷部(彫埋)の漆がムラなく回っているかを確認します。
メンテナンスは柔らかい綿ネルやマイクロファイバーでの乾拭きが基本で、水分・強い摩擦・アルコールは厳禁です。
漆は化学薬品に弱く、ワックスや艶出し剤は曇りや付着を招くため避けます。住環境は温度20℃前後、湿度60〜70%を目安に、桐箱と駒袋で緩やかに守ります。
乾燥剤は過乾燥を招かないよう少量を同梱し、梅雨時は入れ替え、冬場は開放時間を長めに取って急な乾き過ぎを防ぐと安定します。
万一の水濡れは擦らず押し当て吸水し、直射日光やドライヤーでの急乾燥は避けてください。漆への接触で皮膚が敏感な方は、手入れ時に手袋を用いると安心です。
やってよいこと
・柔らかい布での乾拭き(力を入れない)
・桐箱+駒袋で直射日光と急な温湿度変化を避ける
・梅雨/真夏の乾燥剤入れ替え、冬の過乾燥対策
避けること
・アルコール・ワックス
・化学洗浄剤の使用
・濡れた直後のこすり
・ドライヤーでの急乾燥
・強い芳香の防虫剤を直接接触させる
季節別メンテ目安
| 季節 | 目安湿度 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| 春 | 50〜60% | 基本は乾拭き。換気と直射日光回避 |
| 梅雨 | 70%前後 | 乾燥剤追加・箱の開閉で“呼吸”を確保 |
| 夏 | 60〜70% | 高温回避。持ち出し後は早めに乾拭き |
| 秋 | 50〜60% | 乾燥剤を減らし過乾燥を防止 |
| 冬 | 40〜50% | 過乾燥注意。箱を少し開け湿度差を緩和 |
将棋盤の保管の仕方とメンテナンスなどの手順は、駒・盤のお手入れ完全ガイドにまとめました。
失敗しない購入・アップグレードのポイント|
最初は視認性とサイズ感を最優先にし、機械彫→手彫→彫埋→盛上と段階的に上げると違いが実感しやすいです。
アップグレード時は“同一書体・異なる製法”や“同一製法・異なる材”のように比較軸を一つに絞ると、差分が明確になります。
受注生産では納期(数週間〜数か月)、作例、木地等級、書体の揃い、裏字の品位、保証や修理可否を事前確認し、音色や色の相性は手持ちの盤で実機テストするのが理想です。
号数と厚みは手の大きさとの相性が重要で、摘まみやすさと置きやすさのバランスを体験で選びます。返品・調整ポリシーや、将来の塗り直し・角欠け修理の可否も長期満足度を左右します。
既存の入門駒は「持ち出し用」に格下げする発想で無駄を抑え、次点の候補は中古委託市場の相場も参考にすると、資産性と入手難易度の見取り図が描けます。
最終的には、毎日見ても飽きない“顔”と手に収まる“重心”が、長く愛せる一組を選ぶ決め手になります。
アップグレードの道筋(例)
| ステップ | 製法 | 材 | 狙い | 予算感(相対) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械彫 | シャム黄楊 | 実用・視認性・耐久の基盤づくり | 低〜中 |
| 2 | 手彫 | シャム/本黄楊 | 指止まり・線の味を体感 | 中 |
| 3 | 彫埋 | 本黄楊 | 面の整いと陰影で実用と鑑賞を両立 | 中〜高 |
| 4 | 盛上 | 本黄楊 | 立体線と格調。晴れ舞台用 | 高 |
盤との相性で迷う場合は、**将棋盤の選び方(材・サイズ・音色)**を先に確認すると、駒の比較が楽になります。
FAQ
Q1:初心者はまずどの駒を選ぶべき?
A:シャム黄楊の機械彫(標準号数)がおすすめです。視認性・耐久・価格のバランスに優れ、練習から対局会まで使い回せます。
Q2:源平配色はいつまで使う?
A:駒の動きに慣れるまでで十分です。通常配色へ段階移行すると競技環境にスムーズに適応できます。
Q3:駒で初見だとわかりにくい木目や用語ってある?
A:
- 柾目(まさめ:年輪が直線状に出る木目。反りにくく均一です)
- 板目(いため:年輪が山形に出る木目。表情豊かだが反りやすい傾向)
- 玉杢(たまもく:渦状・円形の希少な杢目。鑑賞性が高い)
- 呂色(ろいろ:漆を磨き上げた鏡面仕上げのこと)
- 斜光(しゃこう:45度前後の斜め光で陰影・凹凸を確認する照らし方)
- 号数(ごうすう:駒の大きさ規格。数が大きいほど大ぶり)
まとめ
この記事では、将棋駒の「道具を超えた工芸性」と、製法・材質・書体の違いが生む指し味/視認性/音色の差、用途別の選び方から保管・メンテ、そして高級駒の鑑賞ポイントまでを解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 製法(押し・書き・彫・彫埋・盛上)と木地(本黄楊/シャム黄楊/樹脂)の組み合わせが、触感・陰影・耐久・音色を決める。
- 選び方は「視認性/手触り/鑑賞性」の優先順位+用途・予算で最適化。初心者はシャム黄楊の機械彫や樹脂、ステップアップは手彫→彫埋→盛上。
- 購入前は斜光での見え方・音色・面取り・裏字の品位・反りをチェック。保管は桐箱+駒袋・緩やかな湿度管理(乾拭き徹底)で艶を育てる。
将棋駒選びでは、用途×製法×材×書体×盤との相性を一貫させることが重要なポイントとなります。
購入・アップグレードでは、ここで挙げたチェックリストとを押さえて、あなたの手と盤に合う一組を選んでみてください。
将棋セットの選び方についてもっと詳しく知りたい方は、【初心者必見】失敗しない将棋セットの買い方!予算・種類・選び方のポイントもどうぞ
